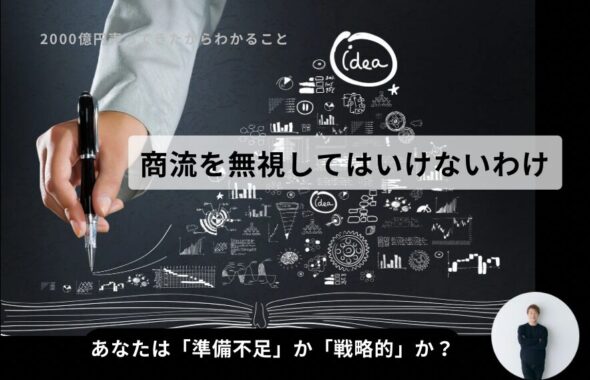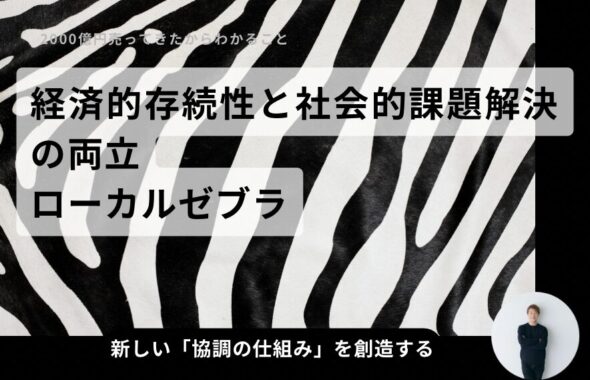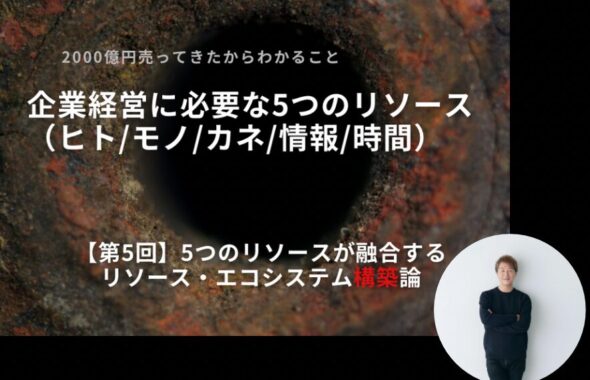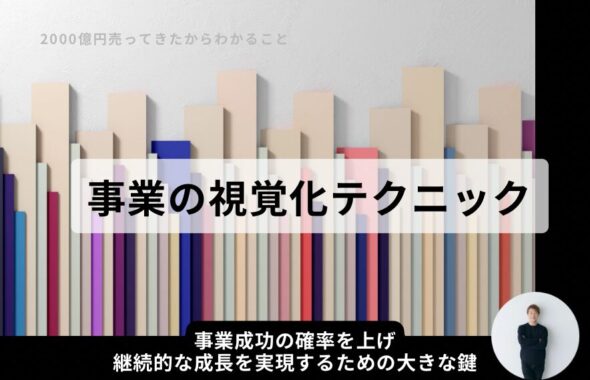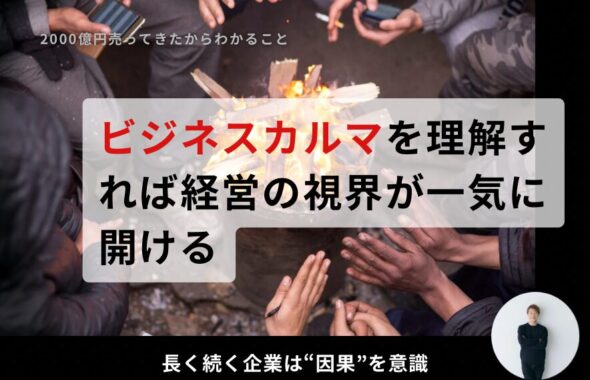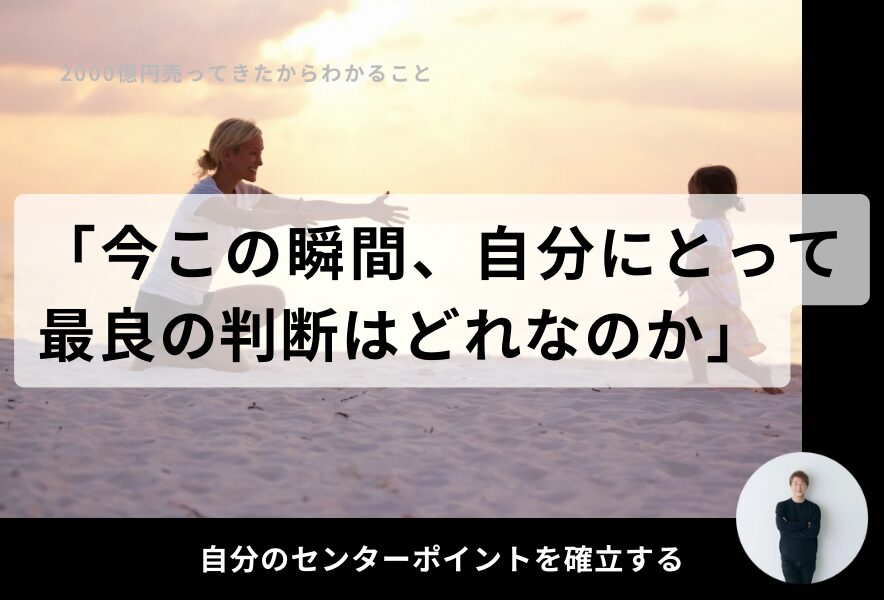
経営における「センターピン」の法則とは?全課題をドミノ倒しにする「核心」の捉え方
経営者や起業家として日々の決断を迫られるとき、どうしても外部の状況に心を揺さぶられやすくなります。景気や競合他社の動向、従業員の意見、顧客の要望など、多様な要素が経営判断に影響を与えますよね。そこで大切になるのが「センターポイント」と呼ばれる考え方です。自分の軸をはっきりと定めたうえで、周囲から流れ込む情報や感情の波をうまく受け止めていく。それが本当に望む方向へ進むための秘訣だと考えられます。
この「センターポイント」という概念は、ビジネス以外のさまざまな分野でも役立てられてきた思考法をベースに、経営に置き換えて再構築したものです。具体的には、人が何かを選択するときの「ぶれない基準点」と捉えてみてください。外部の情報や変化にのまれず、自分が立つ場所と進むべき方向を見失わないための基準点です。
本稿では、経営判断における「センターポイント」をどのようにつかみ、どんな形で活用していけばよいのかを掘り下げていきます。時には自分自身の考え方を内省する作業も伴いますが、これを知っているだけでも日々の経営判断がかなり楽になります。長期的なビジネスの安定と成功確率を高めるためにも、最後まで読んでみてください。
───────────────
Contents
目標とする「センターポイント」とは何か
まずは「センターポイント」というものを、より具体的に説明します。これは、外部環境や感情に左右されることなく、経営者としての自分がどこを目指し、何を大切にしているのかを明確にしておくための“中心軸”のようなものです。
普段、私たちが経営判断をするときには、いろいろな要素が入り混じります。たとえば、
・新しいマーケットの動向
・従業員の意欲やスキルセット
・資金繰りに関するプレッシャー
・自分の家庭の事情や体調
など、仕事とプライベートの垣根を越えて多種多様な情報や感情が絡まってきます。
そのどれもが大切であり、経営を成功させるためには無視できない情報ばかりです。しかし、それらすべてを鵜呑みにしてしまうと、「自分は何を優先させたいのか」がわからなくなってしまい、結果として思考が混乱しがちです。そこで役立つのが、あらかじめ自分のなかに“揺らぎのない基準点”をもっておくという姿勢です。すなわち、その基準点が「センターポイント」です。
───────────────
なぜ経営判断にセンターポイントが必要なのか
経営においては「資源の配分」をいかに決めるかが勝負の鍵になります。ヒトやモノ、カネ、そして経営者自身の時間や思考力を、どこにどれくらい投入していくのか。この判断に迷いが生じると、経営が停滞したり、無駄な投資が増えたりしやすくなります。
経営判断を下すときには、感覚的なひらめきや勇気も大切ですが、最終的には「どの判断が自分の方向性と一致しているか」を考えなければなりません。勢いだけに任せると、なまじリスクを取ることばかりが美徳のように思えてしまい、危険な賭けに出るケースもあります。一方、リスクを恐れすぎてしまうと、守りに入ったままマーケットの変化に取り残される恐れもあります。
そこで、自分が望むビジネスの姿や理念(何を実現したいか)をあらためて定義し、それを日々の経営判断の基点とする姿勢が重要になってきます。周囲からの意見や社会情勢を冷静に見極めつつも、最後は自分自身のセンターポイントを確認し、「今この瞬間、自分にとって最良の判断はどれなのか」を選べるようになる。その積み重ねが事業の方向性を大きく左右します。
───────────────
自分のセンターポイントを確立するために必要な内省
「センターポイントをつくろう」と言っても、いきなり簡単にできるわけではありません。自分はそもそも何を目指しているのか。ビジネスを通じてどんなゴールを実現したいのか。経営者として譲れない価値観は何なのか。こうした問いに真剣に向き合い、自分の内側を見つめ直す作業が必要になります。
例えば、具体的には、
「なぜ自分はこのビジネスを始めようと思ったのか」をノートやPCのメモに書き出してみる。
あるいは、「自分にとって成功とは何を意味するのか」を改めて整理してみる。
というように、目指す未来像をできるだけ言語化してみるとよいです。
経営をしていると、日々さまざまな問題が発生します。トラブルへの対応や、売上アップのための戦術を考えることに追われがちで、本来の理念や大目標を忘れそうになる瞬間が少なくありません。ところが、自分の理念や目指す未来を何度も見直す習慣があれば、どんなに忙しいときでも「自分は何のためにこのビジネスをやっているのか」を思い出しやすくなります。これがセンターポイントを強固にしてくれるのです。
───────────────
センターポイントをつくる具体的ステップ
この思考法をビジネスに落とし込み、実際に経営判断で活かすために、より具体的なステップをいくつか紹介します。
───────────────
ステップ1:自分の価値観リストを作る
まずは、自分がビジネスと人生で大切にしている価値観を洗い出してみます。たとえば「顧客満足」「社会貢献」「自社の利益」「社員の幸福」「イノベーション」「持続可能性」など、多様なキーワードが挙げられるはずです。最初は思いつくままにどんどん書き出してOKです。
そのあとに、それらを優先順位の高い順に並べてみます。「絶対に譲れない」「できれば重視したい」「あれば理想だが無理なら妥協できる」といった感じで、段階的に分けてもよいでしょう。ここで自分の意思と理念が整理されることで、判断軸がクリアになります。
───────────────
ステップ2:ビジョンを一文で言語化する
経営計画や事業計画書には、長々としたビジョンやミッションが書かれていることが多いです。しかし、その文章があまりにも長いと、日々の忙しさのなかで覚えきれず、いつのまにか形骸化してしまうこともあります。
そこで「本当に実現したいことを、一文で言い切る」という作業にチャレンジしてみてください。たとえば「自社の商品を使うことで、〇〇という課題から人々を解放する」といった形です。短い言葉で言い切ることで、自分のセンターポイントとなるビジョンがさらに明確になります。
───────────────
ステップ3:外部情報の取捨選択を定期的に振り返る
ビジネスをしていると、マクロ経済データやマーケットのトレンド、外部コンサルタントの意見、業界新聞の記事など、本当に多くの情報が飛び込んできます。それらの情報が役に立つのは確かですが、情報過多に陥ると「どれが本当に必要な情報なのか」を見失うリスクが高まります。
そこで、一定のサイクル(週に一回や月に一回など)で「今の自分が集めている情報は本当に必要か?」と自問自答してみるのがおすすめです。集める情報を選別し、自分が何を重視してビジネスを動かしているのかを振り返ることで、センターポイントがぶれにくくなります。
───────────────
ステップ4:定期的にひとり時間を確保する
経営者は孤独とよく言われますが、それでも実際には、従業員や取引先、家族など、多くの人とコミュニケーションをとる必要があります。情報のやりとりが増えれば増えるほど、周囲の声に引っ張られることも多くなるでしょう。だからこそ、あえて意識的に「ひとりだけの時間」を定期的につくることが大切です。
例えば、具体的には、
・朝の出社前に30分だけカフェに立ち寄り、頭をクリアにする
・仕事用のスマホとプライベートのスマホを完全に分け、週に一度はビジネスの連絡をシャットアウトする
といった形で、自分とじっくり向き合う時間を確保すると、脳内が整理されてセンターポイントを再確認しやすくなります。
───────────────
経営判断と感情のコントロール
センターポイントを持ち、客観的に情報を分析することは大切ですが、人間である以上、感情は経営判断に少なからず影響を与えます。実際、感情によって無理な投資に踏み切ってしまったり、逆に本来なら挑戦すべきタイミングで怖気づいてしまうケースもあるでしょう。
感情をゼロにすることはできませんし、それ自体が悪いわけでもありません。むしろ、情熱や信念があるからこそビジネスは大きく発展すると言えます。ただし、感情に流されすぎると、目先の損得に翻弄されたり、必要以上に自分を大きく見せようとして判断を誤ったりするリスクが高まります。
こうしたリスクを避けるためにも、「感情が強く動いているときほど、いったん立ち止まる」という工夫をしてみてください。カッとなったとき、すぐに決断しない。悲観的になりすぎているとき、あえてプランBやプランCを検討してみる。そうやって気持ちが揺れているときに一呼吸置くことで、センターポイントに立ち返る余裕を取り戻せます。
───────────────
外部アドバイスと自分の判断のバランス
経営者であっても、すべてをひとりで判断する必要はありません。むしろ、他人の知恵や経験を積極的に借りることで、ビジネスの幅が広がります。信頼できるメンターやコンサルタント、先輩経営者、さらには従業員からの進言など、あらゆる視点を取り込むのは大いに意味があります。
一方で、外部アドバイスが増えれば増えるほど「いったいどの意見を聞いて、どの意見を取り入れないのか」という問題に直面します。ここでもカギになるのが、自分のセンターポイントです。複数のアドバイスを受け取った際、「そもそも自分が求めるビジネス像に近いものはどれか」「自分の価値観や理念と合致しているか」を基準として取捨選択を行うわけです。最後の決断は自分で引き受ける、というスタンスを崩さないことが大切です。
───────────────
センターポイントが導く経営判断の具体例
では、実際にセンターポイントを明確にすることで、どのような経営判断が変わってくるのか。ここでは、いくつかの具体例を挙げてみます。
───────────────
新規事業への投資判断
たとえば、あなたが飲食店を経営しているとします。新たにデリバリー専門の業態に参入するかどうかで迷っている場合、まずは「自分が大切にしたい価値観」と照らし合わせて考えてみます。たとえば「顧客接点を大事にする」という価値観が最上位にある場合、デリバリーで直接接客が減ることに対してどう折り合いをつけるのかが最大の論点になるはずです。逆に「利便性を高める」「売上拡大を優先する」という価値観が最上位なら、デリバリーへの投資はむしろ積極的な一手といえるでしょう。
こうして、一見すると数字やマーケットのデータに基づいた議論に見えながらも、その背景には自分がどんなビジネスを目指しているのか、どのような価値観を重視しているのかが表れています。センターポイントがはっきりしていれば、数字が良い・悪いだけに振り回されず、自分にとって正解と思える決断を下しやすくなります。
───────────────
人材採用・チーム編成
次に、人材採用や組織作りの判断でも、センターポイントは力を発揮します。たとえば、企業文化として「挑戦と失敗を許容する風土を作りたい」という理念が強い場合、人材を採用するときに「過去の成功実績だけでなく、失敗から学んだ経験を積極的に語れるか」という点を評価基準に入れることがあるでしょう。
さらに、社内の人材配置についても、誰をリーダーに据えるかを考える際に「変化に強い人材が求められるマーケット環境かどうか」「安定感を重視したいフェーズかどうか」という経営方針との整合性を見ることで、最適な判断につなげられます。ここでも、経営者自身が大切にする価値観やビジョンがセンターポイントとなって機能します。
───────────────
値上げや値下げに踏み切るとき
製造コストの高騰やマーケット競合の激化など、価格戦略に悩む局面はよくあります。このときも、どのような顧客価値を提供したいかによって判断が大きく分かれます。たとえば「高品質かつ手ごろな価格を実現する」という目標がはっきりしていれば、コストダウンに全力を注ぎ、企業努力で安定供給を目指す判断になるかもしれません。一方で「プレミアム路線でブランドイメージを高める」という方向性なら、原価が上がっても値上げをして利益率を確保する道を選ぶかもしれません。
外部環境の変化は激しく、価格へのプレッシャーも常にかかります。しかし、センターポイントさえ定まっていれば、どちらの選択肢を取るにしても「自分たちはこういうビジョンで商売をしているのだから、この価格戦略でいく」という形で納得感が得られやすいのです。
───────────────
実際に決断を下す流れ
では、センターポイントを持ったうえで、どのように判断を進めていけばいいのか。大まかな流れとしては、以下の手順を意識するとスムーズです。
1. テーマの明確化
「何について判断したいのか」をはっきりさせます。これが曖昧だと、どこまで検討すべきかが分からなくなり、時間も労力も空回りしやすいです。
2. 情報収集
必要なデータや意見、マーケット動向などを可能な範囲で集めます。あまりに多すぎる情報は混乱を招くので、ある程度の段階でストップする勇気も必要です。
3. 自分のセンターポイントと照合
ここが最も大事なステップです。自分が大切にしている価値観やビジョン、そして長期的に見たときにどんな方向へ進みたいかをもう一度思い返します。
4. 一度立ち止まって検証
「本当にこの判断でいいのか」「感情や外部の声に流されていないか」を確認します。可能ならば、一晩寝かせたり、社外の信頼できる人に相談したりしてもいいでしょう。
5. 決断・実行
最後は行動に移し、結果を検証するプロセスに入ります。実行した後に「やっぱり違った」と気づくこともありますが、それも成長の糧にできます。次の判断をより洗練させるための学びとして活かしてください。
───────────────
センターポイントを強固にするためにやっておきたいこと
センターポイントは、一度定義すれば永遠に変わらないわけではありません。経営者自身が成長したり、ビジネス環境が大きく変化したりすると、優先順位や理念にも変化が生まれます。だからこそ、「定期的に見直す」というアクションを忘れないでください。半年ごと、あるいは1年ごとに、自分のビジョンや価値観をアップデートし、改めて軸を設定し直すことが大切です。
また、経営者だけがセンターポイントをわかっていて、社員や関係者には共有されていない状態だと、一枚岩の組織づくりは難しくなります。自分だけが抱えている経営理念を、ミーティングや社内研修などでオープンにし、チーム全体で「私たちは何のために頑張っているのか」を認識できるようにするとよいでしょう。共有が進むほど、会社全体が同じ方向を向きやすくなり、日々の行動にぶれが少なくなります。
───────────────
まとめ
経営判断は常に情報や感情の波にもまれがちです。しかし、最終的には「自分自身がどんなビジネスを望み、どんな価値観を大切にしているのか」という揺らがない基準に立ち返ることが鍵になります。これこそが「センターポイント」です。
たくさんの選択肢があるなかで、「これが正解なのかどうか」と不安になる気持ちは当然ありますが、センターポイントを明確にしておけば、自分なりに納得できる判断を積み重ねることが可能になります。たとえ結果がうまくいかなかったとしても、そこから得られる学びを次に活かすことで、より理想に近いビジネスを形作っていけるのです。
経営者としての道のりは長く、そのなかには不確実性も多く存在します。それでも、センターポイントをしっかり据えて、内なる声を大切にしながら一歩ずつ歩んでいくことで、長期的な成長と成果を掴み取る確率は格段に上がると考えられます。
ぶれない軸をもって、マーケットの変化にも柔軟に対応できるビジネスを作り上げていきましょう。経営判断のたびに自分の中心に戻り、そのうえで最善策を選び取る。そうした姿勢が、企業を長く安定して成長させる原動力となります。今この瞬間からぜひ、センターポイントを意識した経営判断に取り組んでみてください。
───────────────
以上が、経営判断のセンターポイントについての考察です。情報に振り回されず、感情に支配されず、周囲の意見も取り込みながら、自分らしいビジネスの進め方を築いていくための一助になれば幸いです。信念と柔軟性をあわせもった経営者として、ぜひ次のステージへ踏み出してください。