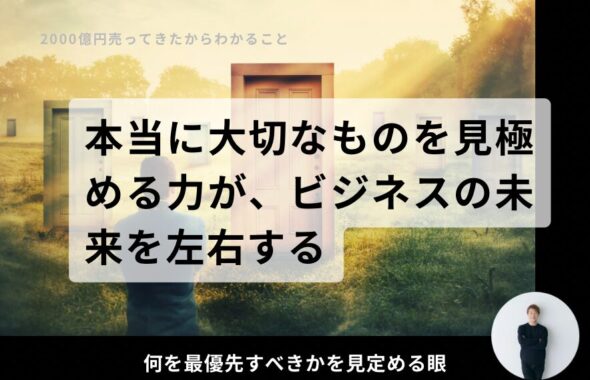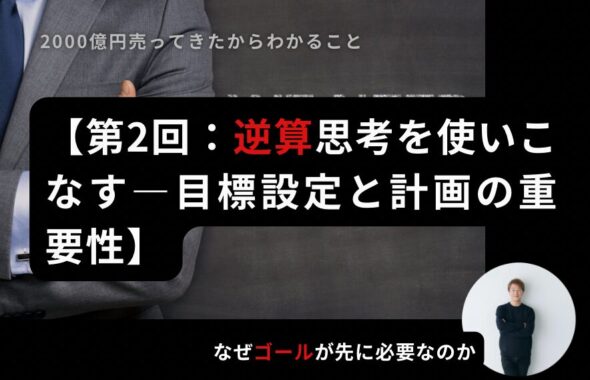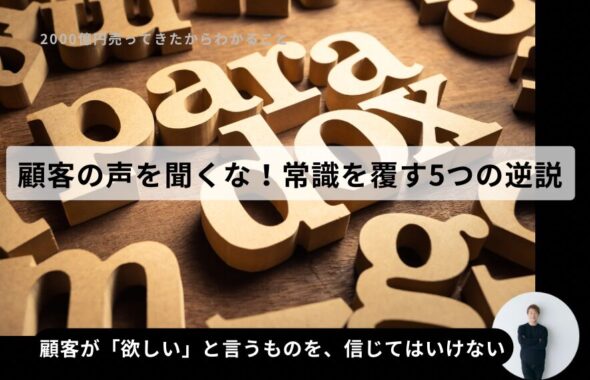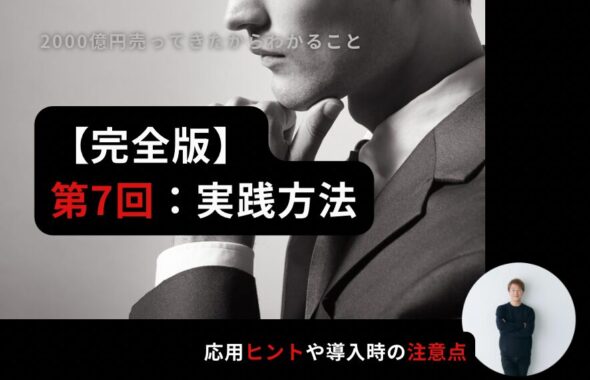成果を妨げる「曖昧さ」を断つ|組織を強くする具体化のルーティン
Contents
なぜ、あの商品は売れるのか?答えは「すごい強み」と「いつもの日常」の掛け算に隠されていた
はじめに:ヒットの裏側にある、たった一つのシンプルな考え方
「どうすれば、もっと売れる商品を作れるんだろう?」
ビジネスに関わる人なら、誰もが一度は頭を悩ませることですよね。市場にはモノやサービスが溢れ、お客様の好みもどんどん多様になっています。そんな中で、多くの人がついやってしまうのが、流行っているものを真似したり、ちょっとだけ機能を良くしたりすること。でも、本当に人々の心をつかみ、長く愛されるヒット商品は、そういったアプローチからはなかなか生まれません。
この記事では、新しい価値を生み出すための、とてもシンプルで強力な考え方をご紹介します。それは私が提唱し、いつもクライアントとのミーティングでお話しするのですが『特異性 × 日常性』というアイデアの掛け算です。難しく聞こえるかもしれませんが、考え方はとてもシンプル。革新的なアイデアは、全くのゼロから生まれるのではなく、実は2つの要素をうまく「掛け合わせる」ことで生まれる、というものです。
ここで言う『特異性』とは、あなた(の会社)だけが持っている、誰にも真似できない「すごい強み」のこと。それは特別な技術だったり、大切にしているブランドの想いだったり、業界の常識を覆すようなユニークな仕組み、あるいは「この人しかいない!」という才能あふれる人材のことかもしれません。
そして『日常性』とは、みんなが普段の生活で「当たり前」にやっていることや、使っているもののこと。でも、ただの日常ではありません。そこには、人々が気づいていない「ちょっとした不満」や「もっとこうだったらいいのに」という隠れた願いが、宝物のように眠っているんです。
この『特異性 × 日常性』という考え方は、「ブルー・オーシャン戦略」という有名なビジネス理論とも深く関係しています。ライバルと争うのではなく、新しい市場(ブルー・オーシャン)を創り出そうという考え方ですが、この掛け算を使えば、その方法が具体的に見えてきます。つまり、お客様の『日常』に隠れた課題を見つけ出し、それを解決するために自分たちの『特異性』(すごい強み)を活かすことで、誰もいなかった新しい市場を創り出すことができるのです。
この記事では、この考え方を分かりやすく解説し、実際の成功事例を紐解きながら、そのパワーを実感していただきます。そして最後には、あなたが新しい商品やサービスを考えたり、今ある事業を見直したりする時に、すぐに使えるヒントとして持ち帰ってもらうことを目指します。
第1部:まずは自分だけの「すごい強み(特異性)」を見つけよう
長く続くビジネスには、必ず他社が簡単に真似できない「すごい強み(特異性)」があります。これは、才能のような偶然の産物ではなく、会社として「これを強みにするぞ!」と決めて、時間と労力をかけて育てていくものです。この「すごい強み」は、大きく分けて4つのタイプがあります。
あなたの会社だけの「すごい強み」を作る4つの柱
- マネできない「技術」 (技術的特異性)
研究開発によって、他社にはない独自の技術を持つことです。これは単に性能が良いというだけでなく、お客様の体験をガラッと変える力があります。例えば、ユニクロの「ヒートテック」は、独自の素材技術で「薄くて暖かい」という新しい価値を生み出し、他の誰も簡単には真似できない強みになっています。また、ZOZOTOWNの「ZOZOSUIT」や「ZOZOMAT」は、「ネットで服を買うとサイズが不安」という多くの人の悩みをテクノロジーで解決し、他の通販サイトとの大きな違いを生み出しました。 - 心を掴む「想い」 (哲学的特異性)
会社全体を導く、強い信念やストーリーを持つことです。これはただのキャッチコピーではなく、すべての判断基準になるような大切な考え方です。Soup Stock Tokyoの「世の中の体温をあげる」という理念は、その素晴らしい例です。この想いがあるからこそ、社員が愛猫を看取った経験から生まれた「猫のためのスープ」のようなユニークな商品が生まれたり、アレルギーを持つ人や赤ちゃん連れのお客様に無料で離乳食を提供したりといった、心温まるサービスが生まれるのです。こうした活動が、ブランドへの深い共感とファンを育てています。 - 業界の常識を覆す「仕組み」 (プロセスの特異性)
その業界の「当たり前」を根本から見直した、独自のビジネスのやり方です。10分カットのQBハウスは、まさにこの「仕組み」の天才です。券売機で先払い、予約はなし、シャンプーの代わりに掃除機のような機械で髪を吸い取る、そして効率を極めた専用のカットスペース。これらはすべて、「髪を切る」という行為を分解し、無駄を徹底的に省くことで、「10分・低価格」という新しい価値を実現しました。 - あの人だからできる「才能」 (人的資本の特異性)
特別な才能を持つ人を仲間にして、その才能を最大限に活かすことです。「俺のフレンチ」の成功は、この点に尽きます。ミシュランの星付きレストランで活躍した超一流のシェフたちをスカウトし、彼らが主役になれる舞台を用意したのです。これにより、料理の味で他を圧倒し、誰も真似できない高い壁を築きました。これは、ただすごい人を集めただけでなく、彼らの才能が輝くビジネスの仕組みをデザインしたからこそ成功したのです。
「すごい強み」は、偶然ではなく、選んで作るもの
ここで一番大切なのは、成功している企業が、偶然すごい強みを見つけたわけではない、ということです。彼らは、お客様の「日常」をじっくり観察し、「ここに困っている人がいる!」という課題を見つけた上で、その課題を解決するために、意図的に自分たちの「すごい強み」を選び、育てているのです。
この順番がとても重要です。例えば、ZOZOTOWNは自分たちの技術力を自慢したくてZOZOSUITを作ったわけではありません。「ネットで服を買う」という日常の中に、「サイズが合わなかったらどうしよう」というお客様の大きな不安があることを発見したからこそ、その問題を解決するための「すごい強み」としてZOZOSUITを開発したのです。
「俺のフレンチ」も同じです。彼らは、世の中の多くの人が「高級レストランの味を試してみたいけど、高くて行けない」と感じていることに気づきました。その満たされない願いに応えるための「すごい強み」として、一流シェフの腕を活かすことを選んだのです。
つまり、「すごい強み」の開発は、閉ざされた会議室だけで考えるものではありません。お客様の「日常」を深く知ることから得られる気づきへの、まっすぐな答えであるべきなのです。この「誰かのために」という想いこそが、この考え方を成功に導く一番のエンジンになります。
第2部:ヒントは「いつもの日常」に隠れている
画期的なビジネスのアイデアは、分厚い市場データからではなく、私たちのありふれた日常に隠された「ちょっとした不便」や「モヤモヤ」から生まれることがよくあります。「日常」をただの市場規模やデータで見ていては、本当のチャンスは見えてきません。大切なのは、一人の人の具体的な体験にグッと近づいて、毎日の生活の中に転がっている「小さな違和感」を見つけ出すことです。
QBハウスが生まれたきっかけも、市場調査のレポートではありませんでした。創業者自身が、床屋さんで体験した「これ、いらないのにな…」というサービスと、それによって失われる時間への個人的な不満だったのです。この話は、私たちが当たり前だと思っていることの中に、いかに大きなビジネスチャンスが眠っているかを示しています。
「日常」に眠るチャンスの鉱脈は、主に3つの種類に分けられます。
「日常」に眠る3つのチャンス
- 「これ、いらないかも?」という小さな不満 (潜在的な不満)
お店側が「お客様のため」と思って提供しているサービスが、実は一部のお客様にとっては「ありがた迷惑」になっているケースです。昔ながらの床屋さんは、丁寧なシャンプーやマッサージ、世間話などを「良いサービス」だと考えていました。しかしQBハウスは、忙しいビジネスマンなどにとっては、これらが価値ではなく、むしろ時間を奪う面倒なものだと見抜いたのです。彼らが本当に欲しかったのは、至れり尽くせりのサービスではなく、「髪を切る」という目的をできるだけ早く達成することでした。 - 「当たり前だと思ってたけど、実は無駄?」なこと (見過ごされた非効率)
お客様が長年「そういうものだ」と受け入れてきたために、もはや問題だとさえ思っていない時間やお金、手間のことです。Netflixが登場する前、人々はレンタルビデオ店に行き、返却日を気にし、延滞料金を払うことを当たり前だと思っていました。Netflixは、月額料金でDVDが家に届き、ポストに返すだけでOKという仕組みで、この「見えない無駄」をなくしました。人々が疑問にさえ思わなくなっていた非効率に光を当て、それを取り除くこと自体が、新しい価値になったのです。 - 「なんとなく、気が引ける…」という心のブレーキ (感情的な障壁)
罪悪感や不安、自信のなさといった気持ちが、何かを始めたり、楽しんだりするのを邪魔している状況です。ロボット掃除機「ルンバ」が日本で広まるのに苦労したのが、この典型例です。当初、売れない理由は価格や性能だと思われていました。しかし、よく調べてみると、日本の文化の中に「家事を機械に任せるなんて、手抜きでは?」という罪悪感や、「自分の手でやらないとキレイになった気がしない」という思い込みといった、心のブレーキがあることが分かったのです。この気づきから、彼らはただ性能の良さをアピールするのをやめ、「どうなの?ルンバ」という実際の利用者の声を使ったキャンペーンで、「掃除を『任せる』のではなく『助けてくれる』パートナー」というメッセージを伝え、この心のブレーキを外すことに成功しました。
「日常」は、常に変わり続けている
ここで忘れてはいけないのは、「日常」は固定されたものではなく、新しい技術や文化の変化によって、常に変わり続けているということです。成功する企業は、今の「日常」を理解するだけでなく、未来の「日常」がどうなるかを予測し、先回りしています。
Netflixの歴史が、まさにそれを物語っています。彼らの最初の成功は、DVDをレンタルするという当時の「日常」をターゲットにしていました。しかし、高速インターネットが新しい「日常」になると、彼らは自分たちの成功モデルを自ら壊し、ストリーミングサービスへと大きくシフトしました。便利な動画の楽しみ方の定義そのものが変わったことを、いち早く察知したからです。
同じように、スマートフォンの普及はネットショッピングの「日常」を大きく変え、ZOZOTOWNやメルカリのような新しいサービスが生まれるチャンスを作りました。
これは、『特異性 × 日常性』のモデルが、一度作ったら終わりではないことを意味します。企業は、自分たちのビジネスがどんな「日常」を前提にしているかを常にチェックし、もしそれが変わり始めているなら、自分たちの「すごい強み」も進化させ続けなければなりません。この変化に対応し続ける力こそが、長く勝ち続けるための鍵なのです。
第3部:「すごい強み」×「いつもの日常」=大ヒット!成功事例を見てみよう
では、「すごい強み(特異性)」と「いつもの日常(日常性)」の掛け算が、どのようにして具体的なビジネスになり、新しい価値を生み出していくのでしょうか。ここでは、4つの成功事例を詳しく見ていくことで、その仕組みを解き明かしていきます。まずは、それぞれのビジネスがどんな構造になっているか、下の表で見てみましょう。
ヒットの構造が一目でわかる!イノベーション・マトリクス
| 企業名 | ターゲットにした「日常」 | 作り上げた「すごい強み」 | 生み出された新しい価値 |
|---|---|---|---|
| QBハウス | 髪を切ること | 時間を最大限に活かすこと(10分カット)、徹底的に効率化された仕組み | 「忙しい人のための、時短・低価格ヘアカット」 |
| 俺のフレンチ | 外食、居酒屋文化 | 一流シェフと高級食材、驚異的な回転率のビジネスモデル | 「一流の味を、居酒屋みたいな価格で楽しめる空間」 |
| ルンバ (日本市場) | 床掃除という家事 | ロボットによる自動化技術 + 家事を「助けてくれる」パートナーという心の価値 | 「掃除から解放されて、自分の時間を取り戻せる生活」 |
| Soup Stock Tokyo | スープという食事 | 「食べるスープ」というコンセプト、心に響くブランドの想いとストーリー | 「心と体を温めて、毎日にそっと寄り添ってくれる一杯」 |
3.1 徹底的な効率化モデル:QBハウス
QBハウスは、1時間4,000円が当たり前だった理美容業界の「日常」をバラバラに分解し、全く新しい形に組み立て直しました。そのやり方は、「ブルー・オーシャン戦略」で使われる「ERRC(取り除く、減らす、増やす、付け加える)」というフレームワークでスッキリ説明できます。
- 取り除く (Eliminate): シャンプー、マッサージ、長々としたおしゃべり、予約、レジでの会計。これらはお客様によっては不要で、時間とお金を増やす原因でした。
- 減らす (Reduce): サービス時間を10分に。価格を3分の1に。お店のスペースも最小限に。
- 増やす (Raise): お客様の回転率を劇的にアップ。駅の中など、便利な場所への出店。
- 付け加える (Create): 券売機、髪を吸い取るエアウォッシャー、そして「ヘアカット専門店」という新しいお店の形そのもの。
ここから分かるのは、QBハウスの成功はただ安くしたからではない、ということです。彼らは、「髪を切る」という日常に、「時間の価値を最大化する」というすごい強みを掛け合わせました。その結果、従来の床屋さんが提供していた「リラックス」を求めない、時間を何よりも大切にする忙しい人たちのための、全く新しい市場を作り出したのです。
3.2 異次元の体験価値モデル:俺のフレンチ
「俺のフレンチ」は、普通なら交わることのない2つの「日常」、つまり「値段の高い高級レストラン」と「安くて賑やかな立ち飲み屋」を分析し、それぞれの良いところを大胆にミックスしました。
- 取り除く (Eliminate): 最初は椅子をなくしました。高級店らしい丁寧すぎるサービスや、広々とした空間も。
- 減らす (Reduce): 料理一皿の値段を高級店の3分の1以下に。お店の内装にかけるお金も。
- 増やす (Raise): 料理のクオリティをミシュランレベルまで引き上げる。食材の原価率を、業界の常識(30%)をはるかに超える60%以上に設定。お客様の回転率を1日に3回以上に高める。
- 付け加える (Create): 「高級ファストフード」とでも言うべき新しいお店のスタイル。行列ができるほどの話題性。
この掛け算は、実に見事です。立ち飲み屋という「日常」のスタイルがもたらす高い回転率と低いコストが、一流シェフの技術と高級食材という「すごい強み」をビジネスとして成り立たせたのです。つまり、片方の日常の良さ(効率)が、もう片方のすごい強み(高品質)を支えるという、お互いを助け合う仕組みを作り上げました。これにより、「一流の味を居酒屋価格で」という、これまで誰も体験したことのなかった圧倒的な価値が生まれたのです。
3.3 新技術をみんなのものにするモデル:ルンバ
ルンバの事例は、「すごい強み」と「日常」の掛け算が、商品の伝え方(マーケティング)においていかに重要かを示しています。日本において、「掃除」という日常は、ただの作業ではなく、家族への思いやりや丁寧な暮らしといった、心の問題と深く結びついていました。
最初のルンバの宣伝は、世界共通で、ロボットの技術的なすごさ(特異性)をアピールするものでした。しかし、このやり方は日本の文化的な「日常」には響きませんでした。そこで、日本のチームは戦略を大きく変えます。
- 戦略の転換: 技術という「すごい強み」は変えずに、その「意味」を変えました。ルンバを単なる「すごい掃除機」から、家事を「助けてくれる」頼もしいパートナーへと、役割を再定義したのです。これにより、ルンバは「家事をサボるための道具」ではなく、「家族との時間など、もっと大切なことをするためのサポーター」として受け入れられるようになりました。
- 伝え方: 実際に使っている人の声を集めた「どうなの?ルンバ」キャンペーンは、人々の「本当にきれいになるの?」という疑問に直接答え、心理的な壁を取り払うのに大きな役割を果たしました。
この事例は、ロボット技術という「すごい強み」を、日本の家庭という文化的な「日常」にうまくフィットさせるために、ストーリーやコミュニケーションの力を最大限に活用したことを示しています。この掛け算は、製品の機能ではなく、その製品がお客様の生活の中でどんな「役割」を果たすかを考え直すことで成功したのです。
3.4 強い想いでファンを作るモデル:Soup Stock Tokyo
Soup Stock Tokyoは、スープという誰もが知っている「日常」に、強いブランドの想いという「すごい強み」を掛け合わせることで、特別な存在になりました。彼らはスープをただの付け合わせではなく、忙しい現代人の心と体を満たす「食べるスープ」として、新しい価値を与えたのです。
- 想いを形に: 彼らの「すごい強み」は、「世の中の体温をあげる」「Soup for all!」というブランドの哲学そのものです。これはきれいごとではありません。アレルギーを持つ人のためのメニュー、噛むのが難しい人のための食事、そして赤ちゃん連れの家族への離乳食無料提供といった、具体的な行動に表れています。これらは大きな儲けを狙ったものではなく、ブランドの信念を形にするための真剣な取り組みです。
- 共感の輪を広げる: この一貫した姿勢が、お客様の深い共感を生んでいます。お客様はただスープを買っているのではなく、ブランドが大切にしている価値観を応援し、その仲間になっているのです。
Soup Stock Tokyoの掛け算は、彼らの心温まる哲学という「すごい強み」を、スープという世界共通の「日常」に適用することで成り立っています。これにより、ありふれた食べ物が、安らぎや思いやり、人との繋がりを感じさせてくれる特別な一杯へと変わり、価格競争とは無縁の、熱いファンに支えられるブランドが生まれたのです。
第4部:さあ、あなたのビジネスで実践してみよう!
『特異性 × 日常性』のフレームワークは、成功事例を分析するだけの道具ではありません。新しい商品やサービスのアイデアをゼロから生み出したり、今あるビジネスを元気にするための、すぐに使える実践的なツールです。ここでは、具体的なシーン別に、どうやって使えばいいかをご紹介します。
4.1 新しい商品・サービス開発のための「日常体験」チェック
この方法は、お客様の毎日に隠れている「まだ誰も解決していない悩み」を見つけ出し、それを解決するあなただけの「すごい強み」を考えるためのものです。
- ステップ1:「日常」のワンシーンを選ぶ
あなたのビジネスに関係する、お客様の日常的な行動を一つ選んでみましょう。例えば、「朝ごはんの準備」「毎日の通勤」「お金の管理」など、具体的で身近なテーマが良いでしょう。 - ステップ2:体験を細かく分解して、「イラッ」「モヤッ」を見つける
選んだ行動の始まりから終わりまでを、ステップごとに詳しく書き出します。そして、それぞれの段階で、お客様が感じていそうな「時間の無駄」「イライラ」「まあ、こんなものかという諦め」「小さなストレス」といった「ひっかかり」を見つけ出します。QBハウスの創業者が、床屋さんでの体験から「待つ時間」や「いらないおしゃべり」という「ひっかかり」を見つけたのが、まさにこのプロセスです。 - ステップ3:「すごい強み」で解決策を考える
見つけ出した「ひっかかり」の一つひとつに対して、それをなくしたり、劇的に良くしたりできる、あなただけの技術や仕組み、サービスを自由に考えてみましょう。これが、あなたが作るべき「すごい強み」のアイデアの種になります。「もし、〇〇という技術があったら、この手間はなくなるのに」「もし、〇〇という仕組みにしたら、この待ち時間はゼロにできるかも」といった問いかけが、新しいアイデアを生むきっかけになります。
4.2 今ある商品・サービスを見直すための「ズレ」発見チェック
時代の変化についていけなくなってしまった既存のビジネスを、今のお客様のニーズに合わせて生まれ変わらせるための方法です。
- ステップ1:自分たちの「すごい強み」をもう一度、言葉にしてみる
今、提供している商品やサービスが持っている、本当にユニークな点は何かを、改めて言葉にしてみましょう。その時、それが今でもライバルとの明確な違いになっているかを、客観的に評価することが大切です。 - ステップ2:「今の日常」を調べる
あなたの商品が生まれた頃と比べて、お客様の毎日の生活、テクノロジーの使い方、価値観、社会の雰囲気はどのように変わったかを、徹底的に調べてみましょう。NetflixがDVDレンタルから動画配信へとビジネスの中心を移したのは、高速インターネットが当たり前になるという「日常」の大きな変化を捉えたからです。 - ステップ3:「ズレ」を見つけて、方向転換する
自分たちの「すごい強み」が、もしかしたら時代遅れの課題を解決しようとしていないか、チェックします。もし「ズレ」があるなら、その「すごい強み」を今の「日常」に合わせて作り直すか、あるいはその「伝え方」を変える必要があります。ルンバが日本で、製品の機能的な価値から「家事を助けてくれるパートナー」という心の価値へとアピールポイントを変えたように、価値の伝え方を見直すことが必要かもしれません。
4.3 新規事業やブランディングのための「物語」作り
人の心に響くブランドストーリーとは、あなたの会社のユニークな「すごい強み」が、お客様の「日常」に潜む問題を、いかに鮮やかに解決するかを語る物語です。このフレームワークは、その物語を作るための強力な骨組みになります。
ブランドストーリーの公式:
「私たちは、あなたが毎日(= 日常性)の中で、[こんなこと] に困っているのを知っています。だからこそ私たちは、独自の [私たちのすごい強み] を使って、[この商品・サービス] を作りました。これを使えば、あなたは [こんな素敵な未来] を手に入れることができます。」
この型にはめて考えることで、ブランディングが単なる自社の強み自慢(特異性)で終わらず、常にお客様の悩みに寄り添う(日常性への貢献)という、共感を呼ぶ一貫した物語として語れるようになります。
まとめ:あなただけの「答え」を見つけるために
この記事でご紹介した『特異性 × 日常性』という考え方は、モノやサービスが溢れる時代に、他とは違う特別な価値を生み出すための、頼れる道しるべです。大切なポイントをまとめると、次の3つになります。
第一に、「すごい強み(特異性)」は、技術、想い、仕組み、才能など、会社として意識的に育てることができる資産であること。第二に、「いつもの日常(日常性)」は、ただの市場ではなく、お客様のまだ解決されていない悩みや、言葉にならない願いが眠る、チャンスの宝庫であること。そして第三に、本当のイノベーションとは、この2つの要素をダイナミックに「掛け合わせる」ことであり、それによって競争に巻き込まれない強いビジネスが生まれるということです。
この考え方が目指す、究極の強みとは何でしょうか。それは、あなたの会社の「すごい強み」が、お客様の「日常」に隠れた、深く複雑な悩みを解決するために、完璧にカスタマイズされている状態です。ライバルは、あなたの機能の一部(特異性)を真似したり、同じ市場(日常性)に参入したりすることはできるかもしれません。しかし、その2つが深い気づきによって結びついた、完璧な「組み合わせ」そのものをコピーすることは、非常に難しいのです。QBハウスの効率的な仕組み、俺のフレンチの品質と安さの両立、ルンバの日本での心の価値の提供、Soup Stock Tokyoの想いが作るコミュニティ。これらはすべて、単なる足し算ではなく、深い洞察に基づいた掛け算の結果なのです。
だからこそ、『特異性 × 日常性』のフレームワークは、一度だけ使うチェックリストではなく、常に心に留めておくべき「考え方のクセ」として、あなたのビジネスに取り入れてみてください。それはきっと、進むべき道を示し、まだ誰も気づいていない本当の価値を生み出し続けるための、信頼できる道しるべとなってくれるはずです。