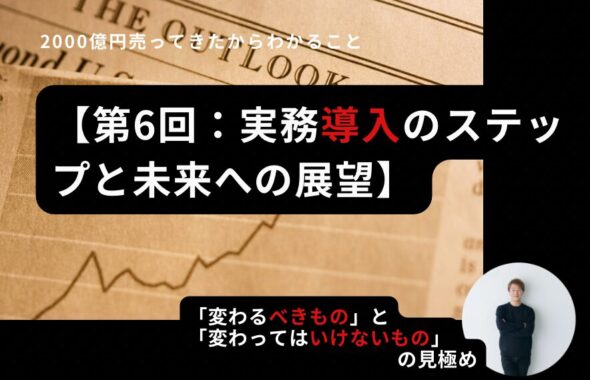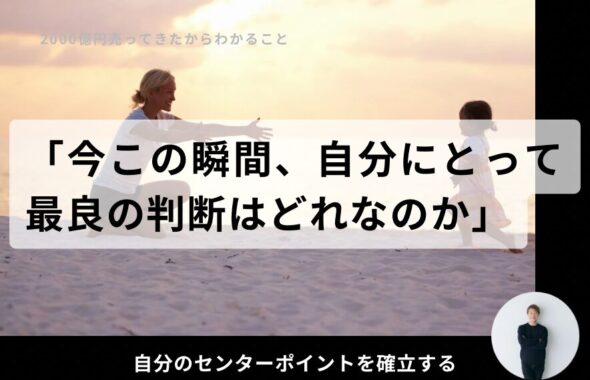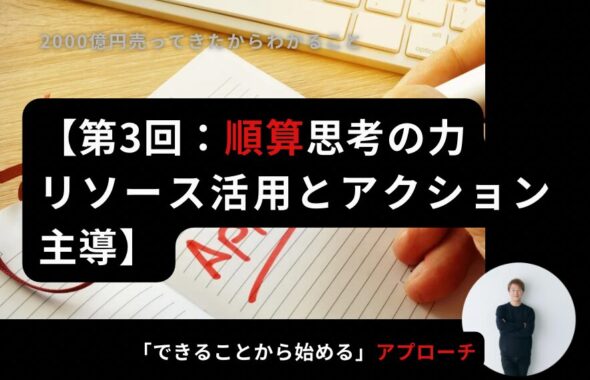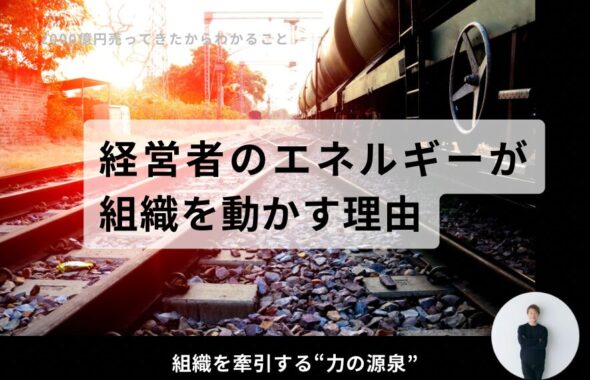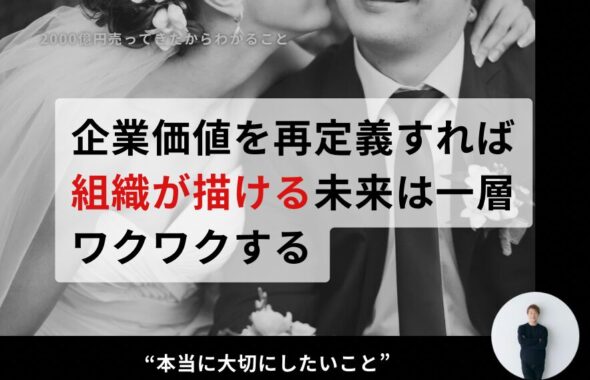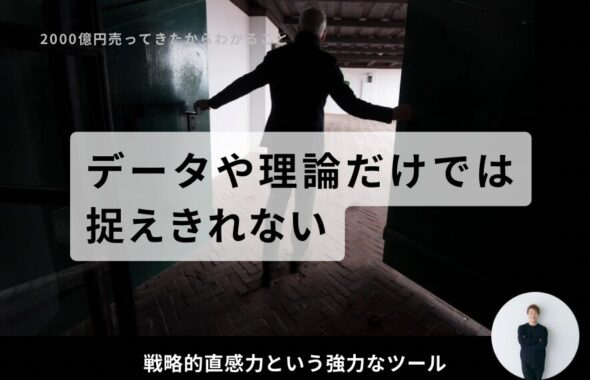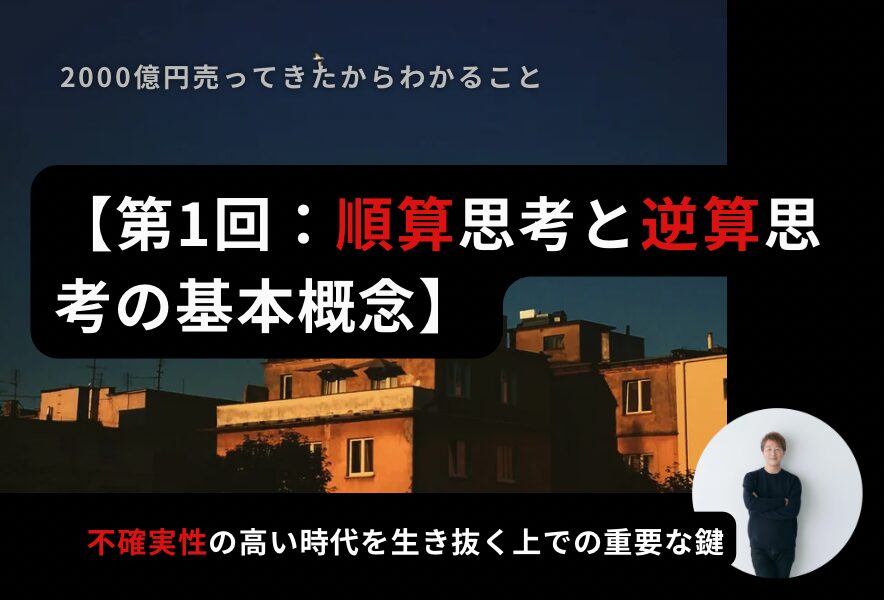
第1回:バックキャスティングとフォーキャスティング|中小企業経営の未来戦略
これまでの実務経験や支援活動を踏まえた形で「なぜ順算思考と逆算思考を組み合わせる必要があるのか」についてまとめています。長文となりますが、ビジネス戦略や組織運営、目標設定に関心を持つ方々の参考になれば幸いです。
────────────────────────────────
Contents
【はじめに】
これまでいくつかの事業を運営・支援し、複数の企業や個人事業主とともに商品開発やブランディング、マーケティングなどさまざまなプロジェクトを進めてきました。事業の規模は小売・サービス・製造業など多岐にわたり、コンサルティングという立場で深く関わることもあれば、自ら事業を立ち上げるケースもありました。
その中で常々感じるのは、「ビジョンを大きく掲げ、その計画を実行するだけでは足りない」一方で、「目の前のチャンスだけを拾い続けていると、最終的に何を目指しているのかわからなくなりやすい」というジレンマです。これは、いわゆる「逆算思考(Backcasting/バックキャスティング)」と「順算思考(Forecasting/フォアキャスティング)」をどう使い分けるか、あるいは統合するかの問題とも言えます。
今回の記事では、この順算思考と逆算思考を組み合わせる必要性や背景、そして実務的に活かすためのヒントを、自分自身が経験してきたプロジェクトや事業支援の事例をもとに詳しく解説します。
────────────────────────────────
【1. 順算思考と逆算思考の基本概念】
1-1. 逆算思考(Backcasting/バックキャスティング)とは
逆算思考は、まず将来のある時点までに達成したい目標を明確にし、その目標から逆向きに必要なステップを遡っていく考え方です。たとえば「3年後に売上を10億円にする」「市場でシェアを10%確保する」など、ある程度具体的な数値や期間を決め、それを軸として「そこに至るまでにどれだけの営業活動や投資が必要か」を一つひとつ算出していきます。
この方法の利点は、組織全体がゴールを共有しやすく、管理指標となるKPIも設定しやすいところにあります。特に企業規模が大きくなるほど、人員配置や投資計画などを長期的に見通す必要があるため、逆算思考をベースにした計画立案は効果的です。しかし、環境が急変したり、当初の想定が大きく外れたりすると、立てた計画そのものを大幅に組み替えなければならないリスクもあります。
1-2. 順算思考(Forecasting/フォアキャスティング)とは
これに対して順算思考は、現時点で持っているリソースやスキル、人脈、アイデアなどを出発点とし、「まずは行動してみる」ことで新しい可能性を切り開いていく考え方です。たとえばスタートアップが試作品を少数だけ作ってユーザーの反応を見る、小売店舗が一部の顧客にテスト販売をする、といった形で「小さく始めて検証し、結果を踏まえて次の一手を考える」ことを重視します。
この方法の利点は、柔軟に方向転換しやすいことや、環境や顧客ニーズの変化を素早く取り込めることにあります。ただし、大きなビジョンがないまま行き当たりばったりで動いていると、組織全体としての統一感が失われ、努力の総和がどこに向かっているのかがわからなくなる危険性もあるのです。
────────────────────────────────
【2. なぜ両思考を組み合わせる必要があるのか】
2-1. 大きな目標と小さな試行錯誤の両立
実務で感じるのは「大きな目標や長期的ビジョンが組織のモチベーションを高める一方で、急な市場変化や環境変化に対応しづらい」という逆算思考の弱点と、「小さく試して学びを得る順算思考はスピード感や柔軟性に優れる一方で、最終的なゴールを見失いやすい」という弱点が、表裏一体になっているということです。
そこで、「目指す最終像はしっかり描きつつ、現場レベルでは新しいアイデアや実験を積極的に試し、結果を見て修正をかける」という統合モデルが効果を発揮します。これにより、将来に向けた大きな方向性がブレにくくなる一方で、日々の取り組みが単なるルーティンワークに終わらず、「まずやってみる」意欲が維持されるのです。
2-2. 変化の激しい業界への対応
私がかつて支援した企業や自分自身が運営するプロジェクトでは、海外との取引条件が突然変わったり、想定外の規制や社会情勢の変化が起きたり、あるいはトレンドの急速な移り変わりが発生するなど、大小さまざまな「予測不能な事態」に直面してきました。こうしたときに、あらかじめ立てた逆算計画どおりに動こうとするだけでは、単に対応が遅れてしまいます。
一方、順算思考を織り交ぜておけば「とりあえずできるところから小さく試す」「新しい方法を素早くテストしてみる」というオプションが常に手元にあり、柔軟に舵を切ることが可能になります。ただ、その際も「最終的にどこを目指すのか」までスッポリ抜け落ちていると、単なる行き当たりばったりになりかねません。この両方を両立させるのが、いわゆる統合的運用モデルの本質です。
────────────────────────────────
【3. 経営支援や事業運営から得た知見:理論と実践の融合】
3-1. コーゼーション(Causation)とエフェクチュエーション(Effectuation)
経営学者の研究では、逆算思考はコーゼーション(Causation)、順算思考はエフェクチュエーション(Effectuation)と呼ばれることがあります。とりわけ起業家の行動を調べた結果、初期の段階ではエフェクチュエーション的(順算思考)に動くことが多く、事業が成長するとコーゼーション的(逆算思考)な計画を強化する、という傾向が指摘されています。
現場での実感としても、設立間もない小規模な組織ほど「始めやすいところから始める」ことが功を奏しやすく、ある程度の売上やファン層を確保した段階で「長期の資金計画や投資回収を逆算しながら考える」必要が出てくる流れをよく目にします。
3-2. 長期的視点と短期的視点の両輪
長期的にはどの市場を狙い、どのくらいの規模を目指すのか。そのためには、どの時点で主要メンバーを採用し、どれほどの予算を広告費に回すのか――こうした要素は、逆算思考が得意とするところです。
一方、「今月はこの新商品をテスト販売してみよう」「想定よりも早くユーザー数が増えているからサイトを増強しよう」「競合が新しいキャンペーンを始めたからこちらも対抗策を講じよう」というように、日々動く現場での意思決定は順算思考に適しています。
両方を組み合わせることで、「短期の状況変化に追随しながら、長期目標にブレなく近づく」というダブルループが可能になります。
────────────────────────────────
【4. 実務での統合モデル活用:具体的な事例】
4-1. 3年後ビジョンと毎月の試行錯誤
あるプロジェクトで取り入れたのが「3年後の売上や市場シェアの目標を数値化し、その達成に必要な顧客数・商品ラインナップを逆算する」という方法でした。プロジェクトメンバーは、この逆算思考によって「何をいつまでに用意するか」を把握できます。一方、3年後の市場環境は当然変わる可能性があるため、毎月あるいは四半期ごとに「今どのくらい達成しているか」「想定外の変化は起きていないか」をチェックし、新たな施策を小規模に試す枠を用意しました。
たとえば新製品をテスト販売して反応が良ければ計画を前倒しし、反応が悪ければ別のアプローチを考える。この順算思考の回し方によって、当初の逆算計画よりも早く成功ポイントを掴むことができたり、時には全く別の市場へ方向転換する柔軟性が生まれたりするのです。
4-2. 地域活性化と巻き込み力
行政や地域振興のプロジェクトを支援する際、「3年後に地域をこんな状態にしたい」というビジョンを掲げることがよくあります。そのビジョンを住民や地元企業が共有しやすい形にまとめるのが逆算思考です。一方で、実際に巻き込みを図るには、イベントをテスト開催したり、SNSで少人数向けの告知をしてみたりと、順算思考的な「まずやってみる」取り組みが欠かせません。
具体的には、商店街の空き店舗を活用した小さなマルシェを開催し、参加者や出店者の手応えを調査。その結果や反応を踏まえて、次回は少し規模を拡大したり、異業種のコラボイベントを実施したりします。ここで生まれる発見を次の計画づくりに反映することで、最終的な3年後ビジョンがより現実味を帯び、幅広い主体が参加しやすくなるのです。
────────────────────────────────
【5. 組織マネジメントへの影響】
5-1. トップダウン×ボトムアップのハイブリッド
逆算思考を組織に導入すると、トップダウンで目標がはっきりするので、従業員一人ひとりの方向性が統一されやすくなります。ただし、目標が細かすぎると現場の裁量がなくなり、創造性やアドリブ力が損なわれる懸念が出てきます。逆に順算思考が強い組織は、各メンバーが自主的にアイデアを出しては行動しやすい文化を作れますが、全体の目標設定が曖昧だとチームがバラバラに動いてしまうリスクがあります。
結局のところ、両方を合わせ「大枠の目標は明確にしつつ、現場レベルでは柔軟に動ける」状態をつくることが最も望ましいと考えられます。リーダーが長期ビジョンを明示し、マイルストーンを設定したうえで、「どのように達成するか」は各チームや担当者の裁量に委ねる。こうすることで、トップダウンとボトムアップの利点を同時に享受できるわけです。
5-2. リーダー育成と思考様式のバランス
リーダーシップ研修や幹部向けトレーニングなどでも、逆算思考と順算思考を両立できる人材は非常に重宝されます。大局観を示しつつ臨機応変に動けるというバランス感覚は、一朝一夕には身につきませんが、例えば以下のような演習を並行して行うと、効果が高いと感じています。
• ビジョン策定ワークショップ:3~5年先の目標を具体的に数字とストーリーで描く
• アジャイル/リーンスタートアップ演習:短期間で試作品やテスト施策を回し、検証し続けるプロセスを体験する
この二つを別々に学ぶのではなく、互いがどのように補完関係にあるのかを理解しながら体験することが肝心です。
────────────────────────────────
【6. 変化の激しい時代に両思考を使いこなす意義】
6-1. VUCA時代への適応
現代はVUCA(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)の頭文字で表されるように、予測困難な変化が続く時代と言われます。逆算思考だけだと、予測が外れたときのリスクが大きく、かといって順算思考だけに頼ると、将来の大きな投資判断をミスするかもしれません。そこで、常に「長期ビジョン×短期実験」のサイクルを回しながら、必要に応じて目標自体も柔軟に見直すダイナミックプランニングが必要になります。
6-2. AI・データサイエンスとの統合
AIやビッグデータの活用が進むにつれ、大量の市場データや顧客データを迅速に分析し、次の一手を計算することが容易になってきました。これは順算思考の「まず動いて結果を分析し、次へ活かす」という流れを大幅に加速させる技術的基盤とも言えます。一方、AIは企業の使命や将来ビジョン、価値観まで定義してくれるわけではありません。そこにはやはり経営者やリーダーが掲げる「逆算思考的な目標設定」と「事業哲学」が必要なのです。
こうしたテクノロジーの進歩によって、「逆算で大きな道筋を描きつつ、日々はAIの分析結果をもとに順算で微調整を続ける」というモデルが、より現実的になってきていると感じます。
────────────────────────────────
【7. 自分の経験を通じて実感したポイント】
7-1. 偶然を活かすためには順算思考が必須
私自身、複数の事業やプロジェクトを手がける中で、たまたま誰かを紹介してもらったことがきっかけで新市場が拓けたり、予想外のコラボが生まれて一気に事業規模が広がるといった事例を何度も目にしてきました。こうした「偶然」を有効に活かすには、順算思考の「とりあえずやってみて、巻き込める人や資源は活用する」という姿勢が大事になります。
7-2. 偶然を成果につなげるには逆算思考が必要
ただし、せっかく良い話が舞い込んできても、「それを最終的にどんな形で事業に反映させるのか」を考えられなければ、大きなビジョンへ結びつきません。目指す長期目標があるからこそ、その偶然をどう使うかが明確になり、結果として成果に変わりやすい。つまり、「偶然」をただの「ラッキー」で終わらせず、「意味のあるステップ」にするのが逆算思考の役割なのです。
7-3. 目標は絶対的ではなく弾力的に運用する
大きな目標や計画を立てたら、それを途中でまったく修正してはいけないと思い込む方もいます。しかし、実務ではむしろ「当初の逆算目標を状況に応じてアップデートし続ける」ことが重要です。急激な環境変化が起きた場合、新たな技術革新が起きた場合、あるいは他社との連携が想像以上の成果を生んだ場合など、予想外のイベントを踏まえて目標を作り直す柔軟性がなければ、逆算思考自体が組織を縛りつける枠になってしまいます。
────────────────────────────────
【8. まとめ:両方の思考が生む未来】
以上、逆算思考と順算思考について、その基本的な意味から実務での統合事例、組織マネジメントや個人のリーダーシップ開発まで、幅広く述べてきました。改めてポイントを振り返ると、以下のようになります。
1. 逆算思考:ゴールを先に定め、未来から現在へ逆向きに手順を組む。組織の方向性や目標意識を揃えるのに有効だが、変化への柔軟性に課題がある。
2. 順算思考:現状のリソースやアイデアからスタートし、小さな実験を積み重ねて学びながらゴールを形づくる。イノベーションや偶然のチャンスを活かしやすいが、大きなビジョンの欠如に陥りやすい。
3. 両者の統合:長期ビジョンを描きつつ、日々は短期アクションで検証し、必要があれば計画自体を動的に修正する。トップダウンの目標設定とボトムアップの行動力を両立する。
この組み合わせこそが、不確実性の高い時代を生き抜く上での重要な鍵ではないでしょうか。実際、テクノロジーの発展や世界的な経済構造の変化などにより、目標を一度決めたからといって、そのまま一気通貫で突き進めるケースはむしろ珍しくなっています。だからといって、最初から目標があやふやだと、組織も顧客も「どこを目指しているのか」わからずに混乱が生じます。
両方をハイブリッドに使いこなすためには、まず経営層やリーダーが「逆算と順算は対立する概念ではなく、補完する関係にある」という理解を深めることが大切です。そして、組織全体にその考え方を浸透させる仕組み(ビジョン共有の場、短期的なアクションレビューの場など)を作ることで、変化に対応しながら一貫した成長を遂げる企業体質が育っていくはずです。
────────────────────────────────
【あとがき:次回に向けて】
今回のテーマは、「なぜ順算思考と逆算思考を組み合わせる必要があるのか」でした。次回以降、「逆算思考を深く理解するための目標設定や計画立案の具体的方法」や「順算思考を現場レベルにどう根付かせるか」「テクノロジーをどう活用して両方の思考を強化するか」など、より具体的な実践論に踏み込んでいきたいと思います。
日々の仕事に追われ、計画どおりにいかないことは多々ありますが、そこから新たなチャンスを見つけるのは順算思考の役割です。一方で、企業や組織を導く立場であれば「何年後にどのくらいの利益やシェアを得るのか」という長期視点を掲げる逆算思考が欠かせません。この両輪が噛み合ったときこそ、ビジネスは思わぬスピードで成果を伸ばしていきます。
自分自身も過去の経験を振り返ると、順算思考で動いた結果が「偶然の出会い」を呼び寄せ、そこに逆算思考で描いていた目標が絡むことで大きな展開につながった――という例は数え切れないほどあります。ぜひ皆さんも、本稿をヒントに「両方の思考」を普段の仕事やプロジェクトで意識してみてください。そうすることで、組織や個人の可能性は格段に広がるはずです。
────────────────────────────────
以上が、「なぜ順算思考と逆算思考を組み合わせる必要があるのか」についてです。引き続き、次回もよろしくお願いいたします。