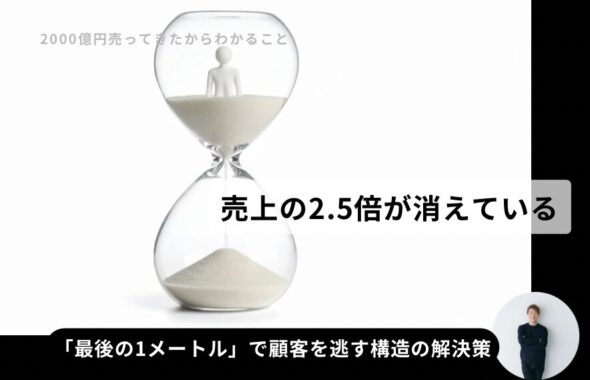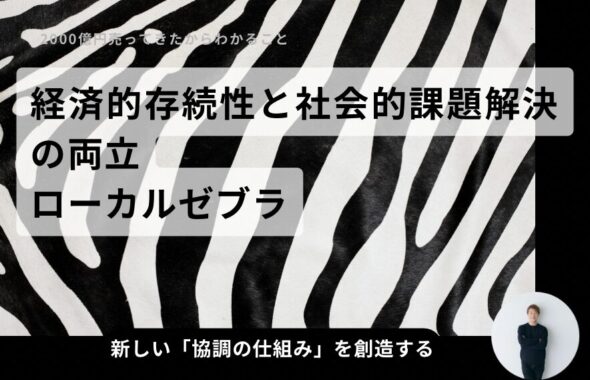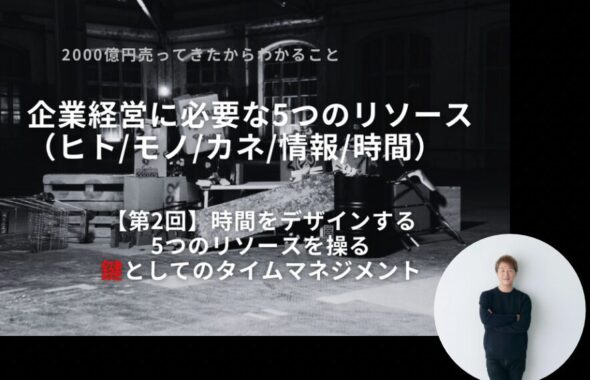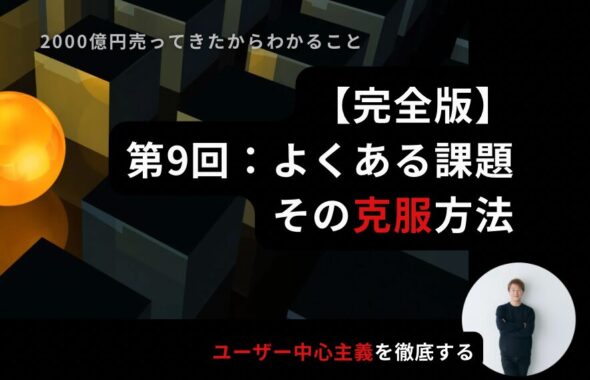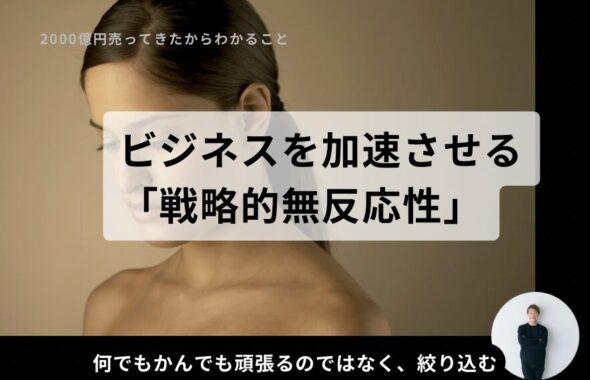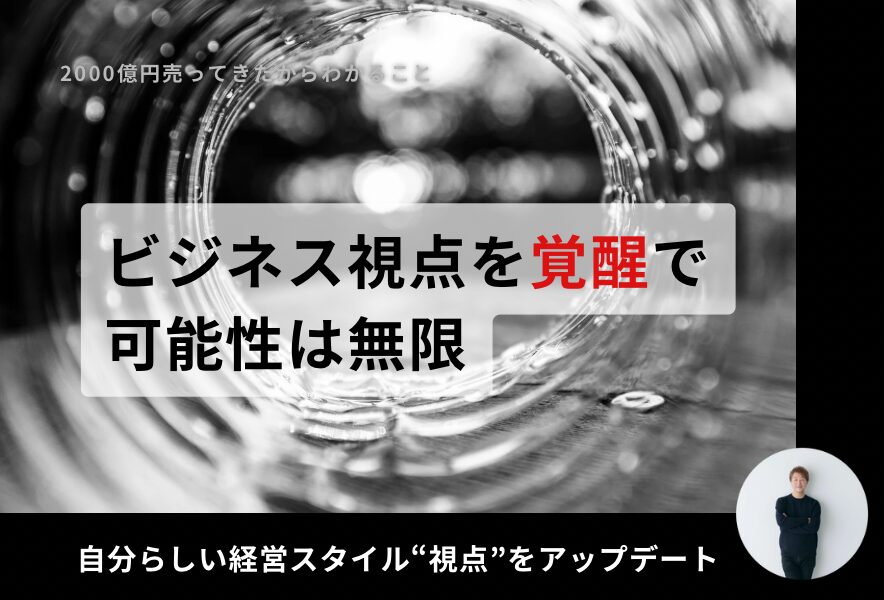
経営の視座を高める|中小企業が未来を掴むビジネス視点
はじめまして。私はこれまで複数の新規事業を立ち上げ、その運営に関わってきました。おかげさまで成功と呼べる成果を得たケースもあれば、試行錯誤の末に撤退せざるを得なかった苦い経験もたくさんあります。そんな実践のなかで、「ビジネス視点を磨くこと」がいかに大切かを痛感しました。
「視点」とはものの見方や価値観のことですが、経営の世界ではこの視点が決定打になることが多々あります。なぜなら、どんなアイデアや戦略も、まずは自分の“目の付け所”が明確でなければ、正しい方向に進んでいかないからです。
では、どうすればビジネス視点を覚醒させられるのか。どうすれば「自分が本当にやりたいこと」をマーケットに届ける方法を見つけられるのか。今回のテーマは、「ビジネス視点の目覚め」です。大きな企業であれ個人事業主であれ、マーケットへ価値を提供し続ける限り、経営者は常に新しい視点が求められます。ここでは、私自身の経験を踏まえながら、多面的な視点を養うための考え方をお伝えしていきます。
Contents
ビジネス視点の目覚めとは何か
ビジネス視点の目覚めとは、「物事を多角的に捉え、本質的な価値を見抜く目を培うこと」です。経営者として事業に携わっていると、どうしても毎日のルーティンワークやトラブル対応に忙殺されがちですよね。すると、ビジネスそのものの大きな流れや、これから先の未来像を見落としてしまうことがあるんです。
しかし、実はビジネスのチャンスは、あなたが意識していない場所にひっそりと眠っています。日常の何気ない場面や人との会話、あるいはマーケット全体のちょっとした風向きの変化など、あらゆるところに「まだ顕在化していないニーズの芽」が潜んでいるわけです。ビジネス視点が覚醒すると、そうした小さなサインをキャッチしやすくなります。
では、どうすれば眠っていた視点が目覚めるのか。実はそれは「ビジネスにおける自分の立ち位置を意識的に変えること」から始まるんです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
立ち位置を変えるだけで見える世界は変わる
たとえば、自分のビジネスを俯瞰して見るクセをつけると、「なんで今まで気づかなかったんだろう」というような新たな事業機会や改善点が浮かび上がってきます。これを私は「視座を上げる」と呼ぶことがあります。同じ場所・同じ仕事・同じ人間関係のなかにいても、視座をグッと高めるだけで、まるで違う風景が見えてくるんです。
私の経験では、ある事業がそこそこうまくいっているときこそ、この俯瞰視点を持つことが大事でした。順調にまわっているように見えていても、意外な落とし穴が潜んでいるかもしれないし、マーケットの潮目が変わりつつあるかもしれない。あるいは、今の状態が次の飛躍のきっかけを秘めている可能性だってあります。
しかし、普段のタスクに追われていると、自分が立っている場所の高さを変えるのは容易ではありません。そこで、一度立ち止まって「本当に今のやり方でいいのか?」と問いかける時間を意識的につくるのです。私の場合は月に一度でも「業務を完全に止めて考える日」を設定し、そのときはあえてデスクを離れ、カフェや少し遠出した先で頭を切り替えるようにしています。そうすると、視座が変わりやすいんですね。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
固定観念をはずす大切さ
ビジネス視点を覚醒させるうえで邪魔になるのが「固定観念」です。たとえば、「この業界はこういうものだ」「このやり方こそがベストだ」といった思い込みがあると、新しい発想が入り込む余地がなくなります。もちろん、業界固有の慣習や定石を学ぶことは大切ですが、それがかえって行動を制限してしまうこともしばしば。
私自身、最初の頃は「こうあるべき」「こうしなければならない」という常識に凝り固まっていました。すると、外からユニークなアドバイスをもらったり、未知の分野とコラボレーションするチャンスが舞い込んでも、最初から「そんなのうちには合わないよね」と排除してしまっていたんです。でも、その一見遠いと思っていた要素が、実は事業を飛躍させる突破口になることがあるんですよね。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
常識を疑う勇気を持つ
では、どうすれば固定観念をはずしやすくなるのか。ポイントは「常識を疑う勇気」を持つことです。マーケットにおいて“当たり前”とされていることをあえて疑ってみると、新たな道が見えてきます。「こうするのが普通だから」「みんなが同じやり方だから」という理由だけで決断している部分があるなら、それは視点の幅を狭めているサインかもしれません。
実際に私が携わったある事業では、“消費者は絶対にこのプロセスを必要とするだろう”と思い込んでいた工程をばっさり省きました。すると意外にも苦情はほとんどなく、むしろスピードアップのおかげで満足度が上がったケースもありました。やってみるまでは「これは外せない」という考えにしがみついていましたが、やってみると「なぜもっと早く省かなかったんだろう」と笑ってしまうような結果でした。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
“感情”を味方にするか、コントロールされるか
ビジネス視点を覚醒するには、理性的な思考だけでなく、自分の感情ともうまくつきあう必要があります。とくに経営者は、プレッシャーや不安、時には興奮や怒りなど、さまざまな感情の波にさらされますよね。感情を無視して突っ走ると、その後に必ずといっていいほど反動がきます。逆に感情に振り回されてしまうと、冷静な判断ができなくなる。
大切なのは、感情を“味方につける”視点を持つことです。ビジネスにおいても、自分の直感やワクワク感を大事にするからこそ、面白い発想が生まれることがあります。また、不安や恐れの感情も、自分が準備不足な部分を知らせてくれる警鐘かもしれません。感情を単純にポジティブとネガティブに分けてしまうのではなく、「なぜ自分はこう感じるのか?」を観察することで、本質的な気づきにつながります。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
客観視できるもう一人の自分を育てる
感情を上手に取り扱うには、「感情に流される自分」と「それを客観視する自分」の両方を内側に育てるイメージを持つといいです。これはいわゆる二重視点とも言われる考え方で、「あ、今自分はだいぶ焦っているな」とか「今ちょっと気分が高揚しすぎてリスクを軽視してるな」という内側の声をキャッチする習慣をつけるんですね。
私自身、最初に大きな投資を決断するときは内心ビクビクしていました。ただ、その不安の裏には「チャンスを逃したくない」「もっと経営の幅を広げたい」という前向きな欲求が隠れていると気づいたんです。すると、不安をないがしろにするのではなく、現実的なリスクを洗い出した上で「本当にやる価値があるのか」を冷静に判断できました。不安を感じる自分も、客観的にそれを見つめる自分も両方必要なんだと学んだ瞬間でした。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
情報に溺れず、本質を見抜く方法
経営をしていると、毎日のように大量の情報が舞い込みます。新しいテクノロジーやサービスが登場し、マーケットのトレンドが変化するスピードも速いですよね。そうした情報を追いかけるのは大事ですが、何でもかんでも飛びついていると「結局、どこに向かっているんだ?」という迷いが生まれてきます。
ビジネス視点の目覚めにおいては、“情報を活かす自分”でいるか、それとも“情報に飲み込まれる自分”になるかが大きな分かれ道です。情報の波に流されるのではなく、自分の事業の本質を見失わないための方法を身につける必要があります。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
自分の軸を決めてから情報を選ぶ
その方法のひとつが、「自分の事業の軸をしっかり言語化する」ことです。つまり、「うちは何のために存在していて、どんな価値を提供するのか」を明確にするんです。ここを言語化しておけば、新しい技術や新サービスを導入するか検討するときも、「この軸に合うかどうか」で判断できるようになります。
たとえば、私があるサービスを立ち上げたときは、「ユーザーが時間と手間を節約できる最適な選択肢を提供する」という軸を決めていました。すると、“新しい機能を追加しませんか?”という提案を受けた際にも、「それはユーザーの手間を省くどころか、かえって複雑にならないか?」と考えられるわけです。結果的に取り入れる情報と捨てる情報の線引きがはっきりしたので、ブレずに方向性を定めることができました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
マーケットの声に耳を傾け、主体的に動く
事業を成長させるうえで、顧客や取引先などマーケットの声は重要です。とはいえ、ただ言われるがままに対応しているだけでは、経営者としての主体性を発揮しきれません。むしろ、「本当に求められているのは何か?」を探るために、あえて顕在化していない問題にも踏み込んでいく姿勢が欠かせないんです。
ビジネス視点の目覚めとは、「受動的に言われたことをやるだけ」から「顧客がまだ言語化していないニーズに応える」へと発想をシフトすることでもあります。顕在化した声にすぐ対応するスピード感も大事ですが、それ以上に「言葉になっていない要望」「このマーケットが求める価値とは何だろう?」と問い続ける姿勢こそが、独自性を生み出すカギになります。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
身近なところに隠れたニーズを見つけるコツ
しばしば新規事業のヒントは、身近なところに潜んでいるものです。たとえば、家族や友人との日常会話を注意深く聞いていると、「こういうのがあったら便利だよね」と言っている場面に出くわすことがあるでしょう。それがすでに多くの人に満たされているニーズならビジネスチャンスになりづらいかもしれませんが、少し切り口を変えるだけでユニークなサービスになるケースもあります。
大事なのは、「それを必要としている人はどれくらいいるのか?」と「自分が得意とする分野で形にできるのか?」の両方を冷静に見極める力です。ここでビジネス視点が研ぎ澄まされていれば、「顕在化していないニーズをどのような形で届けるか」ということをスムーズに考えられるはずです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
行動と振り返りのサイクルを回す
視点が目覚めたとしても、「実際に行動に落とし込む」プロセスを踏まなければ意味がありません。さらに、行動した結果を適切に振り返り、次の一手に活かすことが大切です。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
小さく試してフィードバックを得る
あまりに大きな投資や仕掛けを一気にやると、もし間違っていたときのリスクも大きいです。そこで、ビジネス視点を覚醒して見つけたチャンスを試すときは、まず“小さくテスト”するのがおすすめです。たとえば、限定マーケットでのテスト販売を行うとか、プロトタイプを作って顧客や取引先に率直な意見を聞くとか。そうすることで、実際のデータや反応から次のステップを検討できるようになります。
私が新サービスをリリースするときは、最初に想定顧客のうちほんの一部にトライアルとして使ってもらい、そこから得られたフィードバックを開発に反映させるようにしています。こうすれば、「これはうまくいきそうだ」という感覚があっても、実際にマーケットの声を聞くことで間違いに気づくことができるんです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
振り返りの習慣で視点を広げる
そして忘れてはならないのが「振り返り」の時間です。多くの経営者やビジネスパーソンは忙しく、成功しているときほど振り返りを後回しにしがちです。でも、成功体験が次の成功を保証するわけではありません。むしろ、成功の要因を分析し、どの要素がうまく機能したのかを解明することで、再現性の高いフレームワークを構築できます。
失敗した場合も同様に、なぜ失敗したのかを冷静に振り返ることで、学びを次に活かすことができます。何が事前に想定できて、何が想定外だったのかを整理することが大事です。ビジネス視点の目覚めとは、一度だけ閃いて終わりではなく、行動と振り返りを繰り返すなかで深まり、定着していくものなんですね。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
人との出会いを最大限に活かす
ビジネス視点を磨くうえで欠かせないのが「人との出会い」です。経営をしていると、得意先や投資家、業界の先輩経営者、専門家など、さまざまな人と関わりますよね。実はそうした一つひとつの出会いが、自分の視点をアップデートするきっかけになってくれるんです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
刺激を受ける場へ自分を置く
何か新しいインスピレーションが欲しいとき、セミナーや交流会、コミュニティなど“刺激を受けられる場”に足を運ぶのも効果的です。人から刺激を受けると、自分が当たり前だと思っていた価値観や手法が揺さぶられることがあります。そこから「こんなやり方があったのか!」と一気に視野が広がることがあるんですね。
私もまったく畑違いの勉強会に参加してみて、「これはうちの業界には関係ないかな」と思っていたのに、意外なキーワードが大きなヒントになった経験が何度もあります。自分一人だけで考えているとどうしても発想が内向きになりがちですが、他の分野で結果を出している人の考え方を知ると、思わぬつながりが生まれたりします。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
経営者としての“在り方”を磨く
ビジネス視点の目覚めは、単なるテクニックやノウハウの話ではありません。もっと根本にあるのは「経営者としてどんな在り方を大切にするか」という問いです。自分が目指すビジョンや価値観がはっきりしていなければ、どれだけ情報やスキルを身につけても、どこかで行き詰まってしまいます。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ビジネスと人生の方向性を一致させる
起業家や経営者は往々にして「ビジネスの目標」と「人生の目標」を切り離して考えてしまいがちです。売上や利益、事業拡大を追い求める一方で、自分自身が本当に目指したい生き方や大切にしたい家族との時間を犠牲にしてしまうこともあります。
しかし、本質的な意味でのビジネス視点が目覚めると、「自分の人生の方向性」と「ビジネスのあり方」が自然とリンクするようになります。そこには必ずと言っていいほど、“自分が何を喜びとしているのか”という明確な意識があります。これがブレずにいると、企業がどんなに大きくなっても軸が定まっているので、先々の決断にも迷いが少なくなるんです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
まとめ:視点を変えれば、未来も変わる
ビジネス視点の目覚めは、一朝一夕で完成するものではありません。私自身もまだまだ学びの途上であり、日々新たな発見があります。でも、その都度「あ、こういう視点があったか」「この見方は見落としていたな」と自覚できるだけでも、大きな一歩なんです。
経営者や起業家として新しいチャンスや可能性を掴むために、まずは自分の視点をアップデートするところから始めてみてください。
1. 普段のビジネスを俯瞰して見直す時間を確保する
2. 固定観念や常識を疑ってみる
3. 感情を味方につける工夫をする
4. 情報を追いかけるのではなく、選別する軸を持つ
5. マーケットの声を掴みつつ、主体的な発想を大切にする
6. 行動と振り返りをセットで繰り返す
7. 人との出会いから新たな着想を得る
8. ビジネスと人生の方向性を一致させる
このようなステップを実践していくと、意外なほどに「視点が変わったな」と感じる瞬間が増えてくるはずです。そしてその変化が、あなた自身のビジネスを新しいステージへと導いてくれます。
ビジネス視点を目覚めさせることは、決して難しいことではありません。ちょっとした意識の持ち方と、日々の行動を見直す勇気があれば誰にでも始められます。もし「最近マンネリ化している」「次の一手が見えない」と感じているなら、ぜひここでご紹介した考え方や行動を試してみてくださいね。
あなたのビジネスがより充実し、長く続く企業づくりにつながることを心から願っています。これからも一緒に、新しい可能性を探っていきましょう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
以上が「ビジネス視点の目覚め」についての私の考えです。自分の内面と向き合いながらマーケットの声に耳を傾け、同時に新たな情報や人との出会いを積極的に活かす。そんなふうに視点が広がっていくと、アイデアや機会が目の前に現れたとき、それを逃さず掴む力が自然と高まっていきます。
これを読むことで、少しでも新しい気づきや実践のヒントが得られたなら幸いです。私自身、まだまだ学ぶことは多いですが、これまで事業を運営してきた経験から「視点の変化こそがビジネスを飛躍させる原点である」という確信を持っています。あなたもぜひ、今日から意識的に視点を変えてみませんか。
これからのビジネスライフが、より豊かで刺激的なものになることを願っています。