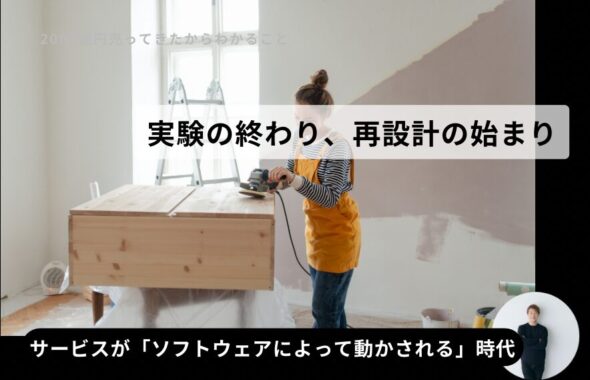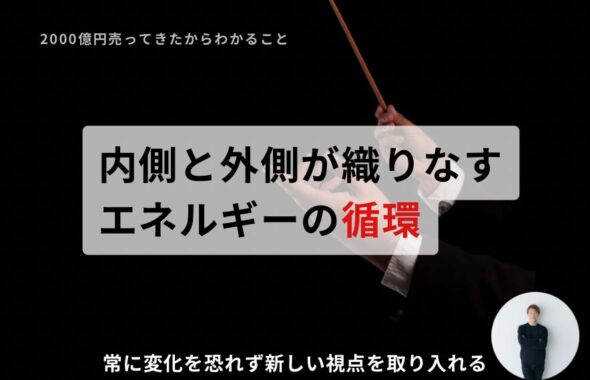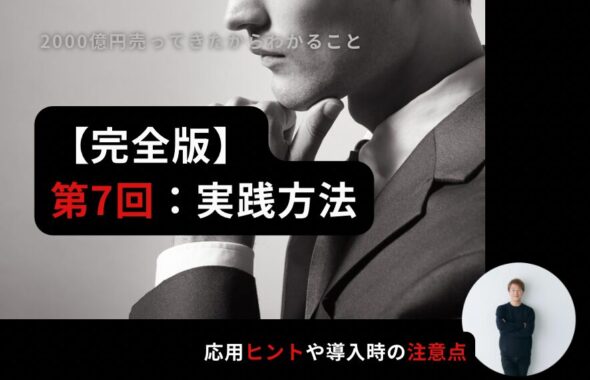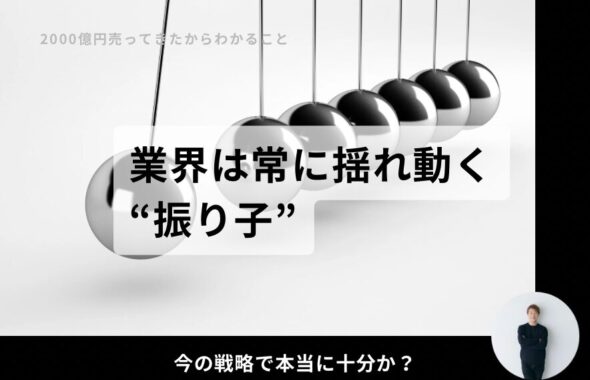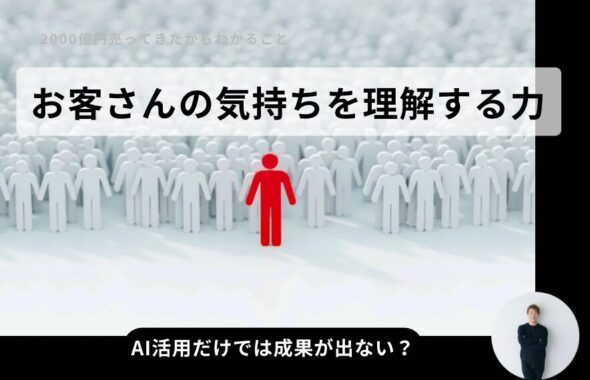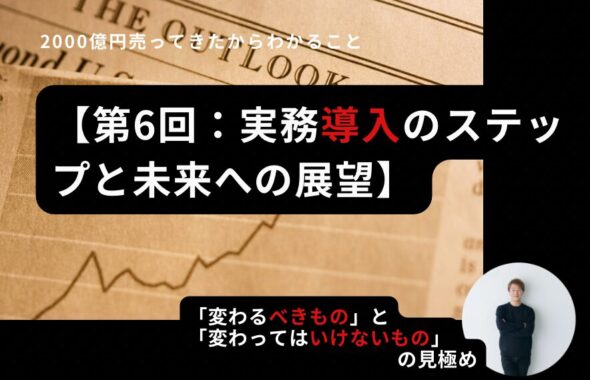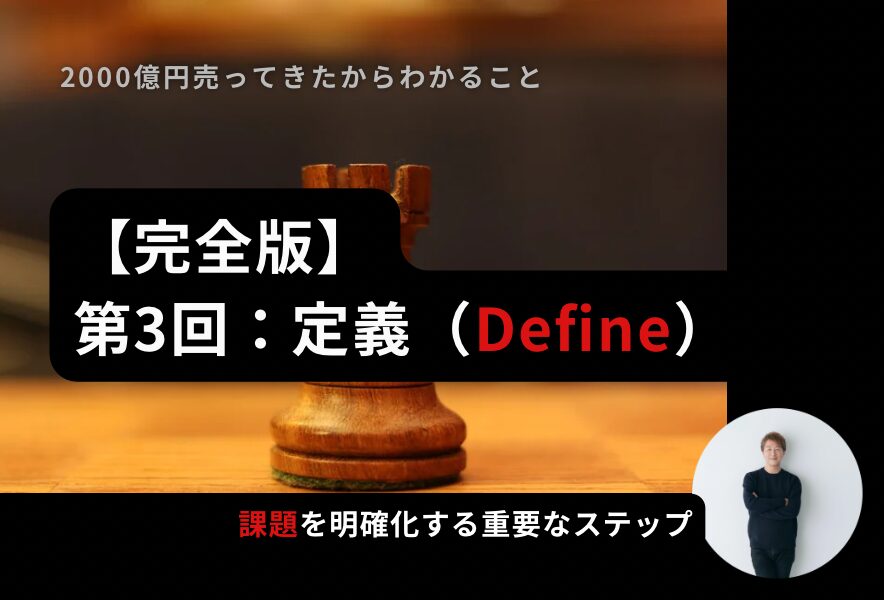
第3回:定義(Define)の力|中小企業経営に不可欠な課題設定
Contents
課題を明確化する重要なステップ
────────────────────────
1. はじめに
────────────
こんにちは!前回の第2回では、デザイン思考の最初のステップ「共感(Empathize)」に注目し、ユーザーの行動や感情を深く理解する方法をお話ししました。共感によって得られる情報は膨大で、多様なインサイトが得られますが、それを整理して“本当に解決すべき課題”を明確にするのが今回のテーマである「定義(Define)」というステップです。
私自身、ファッション業界からスタートし、飲食や建築、さらには経営コンサルへと活動範囲を広げてきました。最近では都内のIT企業で顧問を務めたり、海外投資家の日本向け投資コンサルも行っています。これら異なる分野での経験は、すべてデザイン思考をベースにした「ユーザー中心の発想」「現場目線での課題定義」に支えられてきたと感じています。業種を超えても共通して重要なのは「誰の、どんな問題を解決するのか?」をはっきりさせること。その一貫性が成果をもたらすカギとなります。
今回の記事では「定義(Define)」とは何か、なぜこれほど重要なのか、そしてどのように進めれば効果的かを、具体的な手順や事例を交えながら解説していきます。
────────────────────────
2. 定義(Define)とは何か?
────────────
2-1. 共感で得た情報を整理・分析するステップ
デザイン思考は「共感→定義→アイデア→試作→テスト」という5つのステップで構成されます。前段の共感フェーズでは、あえて膨大な情報を幅広く集めるため、そこからユーザーにとって最も重要な課題を抽出しないまま先に進むと、プロジェクトが混乱しがちです。定義フェーズは、共感で得た観察記録やインタビュー内容などを丁寧に仕分けして、本質的に解決すべき問題を浮かび上がらせる段階になります。
2-2. 「誰のために、何を解決するのか」を明確にする
定義フェーズのゴールは、「私たちはどんなユーザーの、どんな課題を、なぜ解決しようとしているのか?」をはっきりと言語化することです。ビジネス視点だけに偏ると、「自社の売上をどう伸ばすか?」といった方向へ行きがちですが、デザイン思考の原則では「ユーザーが本当に困っている事柄」に焦点を当てなければなりません。解決すべき課題が明確になれば、次のアイデア創出や試作で迷いにくくなり、プロジェクト全体に軸が生まれます。
────────────────────────
3. 定義が重要な理由
────────────
3-1. 問題解決の方向性を明確にする
もし「何を解決したいのか」が曖昧なままだと、いくらアイデアを出しても散漫になり、まとまりのない結果に終わってしまいます。定義によって問題の焦点を絞ることで、アイデア創出(ブレインストーミング)などの創造的プロセスが目的に沿って機能しやすくなるわけです。
3-2. チーム全員の認識を揃える
共感の段階では、チームメンバー各自が収集した情報から異なる仮説を持っている場合があります。誰かは「ユーザーのUXが最大の問題」と考え、別の人は「価格設定が原因」と思っているかもしれません。定義フェーズで「ここが最優先の課題だ」という共通認識を築くことで、チームとしてまとまった行動を取りやすくなります。
3-3. ユーザー視点を維持する
ビジネスの都合上、企業サイドの目標に引っ張られがちですが、定義ではあくまでユーザーの声や行動に基づいてゴールを設定するのがポイントです。ユーザー視点で課題を捉えると、意外な改善ポイントや新たなビジネスチャンスが見えてくることも多々あります。
────────────────────────
4. 定義プロセスの進め方
────────────
ここでは、定義を行う際に代表的な3つのステップを紹介します。いずれも「ユーザー目線を崩さない」ことが大前提です。
4-1. 情報の整理と分析(クラスタリング、インサイト抽出)
まずは、観察やインタビュー、アンケートなどで得た情報を一つひとつ検証します。よく使われる手法は「付箋を使ったクラスタリング」で、ユーザーの発言や行動パターンを付箋に書き出し、似たようなテーマでまとめていきます。こうすることで、大量の情報から共通点や対立点が浮かび上がりやすくなります。
• クラスタリング
膨大な情報をグルーピングし、「ユーザーが実際に感じている不満は何か?」を俯瞰する。
• インサイト抽出
グルーピングされた結果から、ユーザーの潜在的な欲求や、背景にある心理的要因を読み解く。ユーザー自身も気づいていない本音がここで現れることもあります。
4-2. ペルソナ作成
次に、誰のために課題を解決するのかを具体化するために「ペルソナ」を作成します。ペルソナとは「架空の典型的ユーザー像」であり、名前や年齢、ライフスタイル、価値観、抱えている悩みなどを細かく設定します。私の経験上、ペルソナを設定すると、社内やチームで「この人だったらどう思うだろう?」と話し合うときに実感が伴いやすくなります。
例:
• 名前:田中花子さん(28歳、都内在住のIT企業勤務)
• 趣味:SNS閲覧、カフェ巡り
• 課題:忙しい朝に時短でメイクや身支度をしたいが、オシャレも捨てたくない
4-3. 問題文(Problem Statement)の作成
最後に、課題を簡潔な1文(もしくは数文)にまとめます。これを「問題文(Problem Statement)」と呼びます。
• ユーザー視点で書く
「我が社の売上が伸びない」のではなく、「ユーザーが○○で不満を抱えている」という書き方にする。
• 解決策を含めない
「こういうサービスを提供したい」ではなく、「ユーザーは何に困っているのか」を明確にする。
• 具体的かつシンプル
漠然とした「なんとなく不満」ではなく、いつ、どこで、どう困っているかを書き込むと有効です。
────────────────────────
5. ビジネス現場での定義プロセス活用例
────────────
このラインより下のエリアがnoteでは有料で表示されます。
5-1. Uber Eats:忙しい人々の食事準備問題に着目
Uber Eatsが支持を得た背景には、「忙しく働く人々が食事の準備に時間を取られたくない」という明確な課題設定があります。これは単に「デリバリーサービスを展開する」という事業アイデアではなく、「忙しい人々の時間と労力を削減する」というユーザー視点の問題定義がベースにあったからこそ、サービス設計が一気通貫で進められました。
5-2. Dyson掃除機:根本的な不満を掘り下げた技術開発
Dysonの掃除機は「吸引力が落ちない」という独自のUSP(Unique Selling Proposition)で市場を席巻しました。ここには、「一般的な掃除機は使うほど性能が下がる」というユーザーの不満を突き止めた課題定義が存在します。課題が明確になったことで、サイクロン技術など革新的なアイデアに集中投資でき、Dysonブランドの差別化に繋がったのです。
────────────────────────
6. 私が手掛けた事業における「定義」の実践
────────────
これまでファッションや飲食、建築だけでなく、経営コンサル、都内IT企業の顧問、さらには海外投資家向けの日本投資コンサルなど、多彩なプロジェクトに関わってきました。共感フェーズで得られた大量の情報をどのように「定義」に落とし込んだか、その具体例をいくつか紹介します。
6-1. ファッションブランド経営での着眼点
ファッションビジネスは流行やブランドイメージに注目しがちですが、結局は「どんな人がどんなシーンで、どんな気持ちを求めているか?」に立ち返る必要があります。共感フェーズで得られた声を整理して、ペルソナとして「仕事もプライベートも全力で頑張る20代後半女性」を設定し、「平日の職場でも週末の遊びでも着回せるような利便性を求めている」という問題文を作りました。そこからミニマルで機能的なデザインに注力することで、作り込みの方向性が明確になったのです。
6-2. 飲食ビジネスのメニュー開発
飲食店ではメニューの魅力や調理時間の短縮が多くの課題として浮上してきます。例えば、「夜は短時間でしっかり食べたい」という声が多い場合、「忙しいビジネスパーソンが、仕事帰りにサクッと栄養のある食事を手軽に楽しめないのが不満」という問題定義に落とし込む。ここに至ると「調理時間を短縮する」「注文フローを簡易化する」など、具体的な改善策が自然に導き出せるのです。
6-3. 建築・空間デザインのコンサル
建築業界では、施主やデザイナーの希望と、実際に使うユーザーの希望がズレているケースがよくあります。共感フェーズで「利用者は子育て中で、安全と快適性を何より重視している」ことが分かったら、「見た目のデザインを優先するあまり、動線や収納が不便になっている」ことが問題だと定義できます。具体的には「小さな子どもを抱える家族が、日常の家事動線を無駄なくスムーズに進められない」という形にまとめることで、設計方針がユーザーに寄り添うようになります。
6-4. IT企業顧問や海外投資家向けコンサルへの応用
近年は都内のIT企業で顧問を務めたり、海外投資家向けの日本進出コンサルも行っています。ITプロジェクトだと「ユーザーにとって画面やフローがわかりづらい」などの声が出てきますし、海外投資家向けだと「日本の商習慣が不透明で投資判断が困難」という課題が表出することも少なくありません。いずれの場合も、まずは共感フェーズで得た情報を整理し、「どのユーザーが、どんな背景で、どんな困難を抱えているのか」を明確にする定義作業を行います。例えば海外投資家の場合は「日本語や文化的壁が原因で、投資先とのコミュニケーションが円滑に進まない」ことを問題として設定すれば、その後のサポート体制やITツール導入の方向性がはっきり見えてきます。
────────────────────────
7. 定義プロセス成功へのポイント
────────────
7-1. ユーザー視点から離れない
定義の場面で最も注意すべきなのは、企業や組織の利益目線で課題をまとめてしまうことです。もちろんビジネスとしての売上・利益は重要ですが、デザイン思考では最優先が「ユーザーへの価値創出」です。ユーザー視点を中心に据えた問題文がブレない限り、アイデアや試作でも迷走しにくくなります。
7-2. シンプルさと具体性
問題定義が冗長すぎると、チーム内で意見の食い違いが起こるリスクがあります。なるべく短いフレーズで、誰が、どこで、どんな問題に直面しているのかを書き込むことが重要です。私もペルソナ設定の際には無数のシチュエーションを想定してしまいがちですが、敢えて「最も大きな課題」を一つに絞ると成功しやすくなります。
7-3. チーム全員で共有する
定義はプロジェクトの羅針盤です。作業担当だけがわかっていても、経営層や他部門の協力が得られなければ成果につながりにくいでしょう。定義した問題文やペルソナは早めにチーム全員にオープンにし、フィードバックを受けながら共通認識を作ることをおすすめします。
────────────────────────
8. まとめと次回予告
────────────
今回はデザイン思考の5ステップのうち、「定義(Define)」を深掘りしました。共感フェーズで収集した膨大な情報を整理し、ユーザー視点で「誰の、どんな課題を、なぜ解決するのか」を明確化することで、その後のアイデア創出や試作・テストがブレの少ない形で進められます。改めて重要ポイントをまとめると以下の通りです。
• 定義は、共感フェーズで得た情報を“本質的な課題”へと絞り込む作業
• ペルソナや問題文を用いて、ユーザー視点の課題をシンプルに言語化する
• チームの認識を一致させ、ビジネス都合ではなくユーザーの価値を最優先に考える
私がファッション・飲食・建築・IT・海外投資コンサルなど、さまざまな領域に携わる中で痛感してきたのは「定義の精度が高いほど、後の工程がスムーズで、成果が目に見えて向上する」ということです。どの業界でも共通する「人間中心のアプローチ」が、デザイン思考の核心なのだと改めて感じます。
次回(第4回)は、いよいよ「定義」した課題を起点に、新たな解決策を幅広く生み出していく「アイデア創出(Ideate)」のステップを扱います。ブレインストーミングのやり方や、創造性を引き出すためのテクニック、チームで意見を出し合う際のポイントなどを紹介しますので、ぜひお楽しみに。
────────────────────────
(約10,000文字)
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。定義(Define)は地味に見えて、実はプロジェクト成功の要とも言える大切な工程です。誰のどんな課題を解決するのかを明確にすることで、あらゆるビジネス活動やサービス開発が軸を持って進められます。次回は「アイデア創出(Ideate)」で、具体的に解決策を広げるステップを一緒に学んでいきましょう。