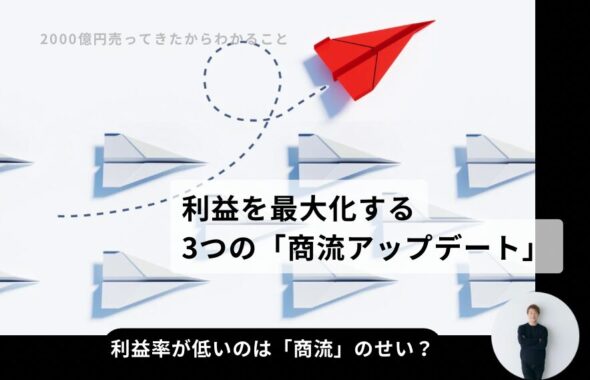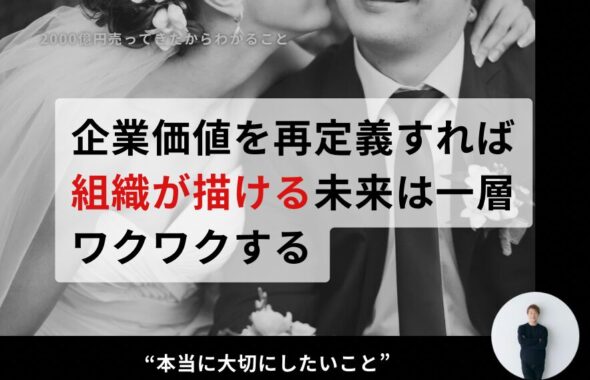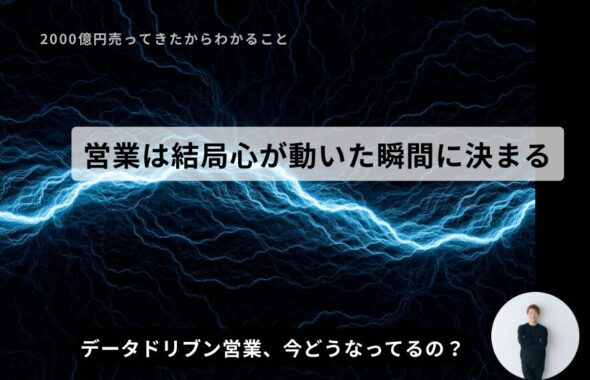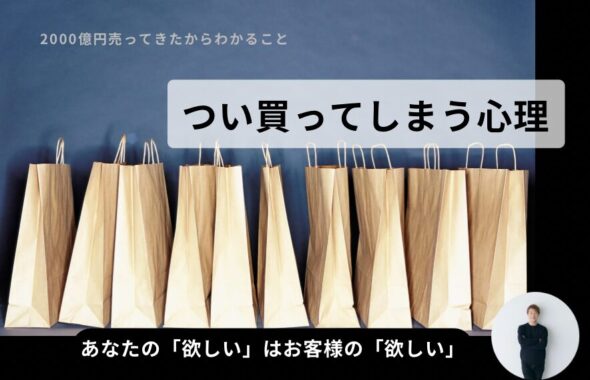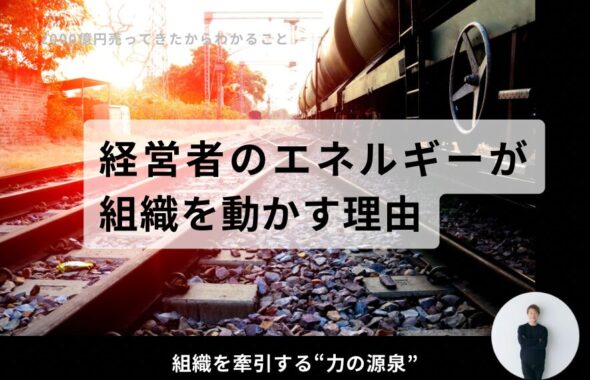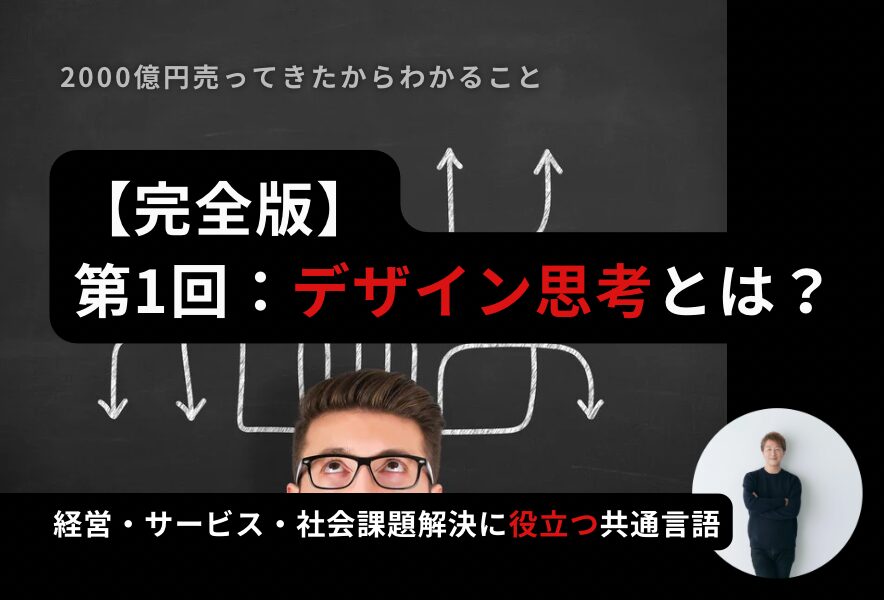
第1回:デザイン思考とは?中小企業経営を変える実践的アプローチ
Contents
概要と特徴
1. はじめに
────────────
みなさんは「デザイン思考」という言葉を聞いて、どのようなイメージを抱くでしょうか。デザイナーが何かを創るときの発想術? あるいは、外観の美しさを追求するための技法? 実際には、デザイン思考はあらゆる分野で活用できる汎用的な問題解決プロセスとして、近年とても注目されています。革新的な商品開発から、社会課題の解決に至るまで、幅広く応用されているのです。
私自身、キャリアのスタートはファッション業界からでした。しかし、その後ファッションブランドの経営や建築業界、エステサロン、飲食業などの複数事業を手掛けるようになり、それぞれ異なる領域でも事業を成功へと導くためには、実は同じ発想やプロセスが不可欠であると強く実感しました。いま振り返れば、それこそが「デザイン思考」に基づくアプローチだったのです。
現在は経営コンサルタントとして、多様な業界・企業の成長を支援していますが、そこでの土台となっているのも間違いなくデザイン思考の考え方です。本稿では、「デザイン思考とは何か?」という基本概要を紐解くとともに、私の実体験を交えながら、デザイン思考がなぜさまざまな業種・職種に応用可能なのか、そして今の時代にこそ求められる理由を説明していきたいと思います。
────────────────────────
2. 私のキャリアとデザイン思考
────────────
2-1. ファッション業界から他業界へ広がった経験
私が社会に出て最初に関わったのはファッション業界でした。アパレルの企画やブランド運営を担い、お客様に喜んでもらうためのデザインやコンセプトづくりに取り組む日々。華やかなイメージがある一方で、実務面では常に「シーズンごとのトレンドをいち早くキャッチする」「顧客の潜在的な要望をいかに先読みして商品に反映するか」など、かなり奥深い問題解決の連続でもありました。
その後、私自身がファッションブランドの経営に携わり、さらに建築業界やエステサロン、飲食業など、まったく異なる領域でも事業を展開する機会に恵まれました。それぞれの業界には独自の文化や顧客属性があります。しかし、ユーザーのニーズを的確に捉え、それに応じた新しい企画やサービスを設計・提供するプロセスは驚くほど共通していたのです。
2-2. デザイン思考の本質を体感したプロセス
ファッションから建築、エステ、飲食と事業領域を横断してきた私ですが、やることは常に「目の前のお客様や生活者に寄り添い、観察し、何が本当に欲しいのかを想像し、それを形にして提案する」という点で一貫していました。
例えば、新しい飲食店を立ち上げる時、立地条件やメニュー構成、内装設計などを考える際にも、「誰が・いつ・どんな気分で訪れ、何を求めているか?」を徹底的にイメージするところからスタートします。これはファッションの企画で、「どんなシーンで着るのか?」「どういうライフスタイルを持つ人がこのブランドを愛用するのか?」を考え抜くプロセスと全く同じでした。
後から知ったことですが、このような発想法がまさに「デザイン思考」のエッセンスだったのです。ユーザーへの徹底した共感に始まり、問題やニーズを明確化し、アイデアを幅広く検討しながら試作を行い、フィードバックを通じて改良する――ファッションでも建築でもエステでも飲食でも、私は自然とこのプロセスを実践していたのだと気づきました。
2-3. 経営コンサルタントとしての現在に繋がる理由
そして今、私は経営コンサルタントとして、多様なクライアントの成長を支援しています。コンサルタントという仕事は数字や計画書を扱うだけではありません。クライアント企業の現場に入り込み、お客様(エンドユーザー)との接点を確認し、経営者や従業員の声を聞き取る。そこから得られたインサイトに基づいて戦略や施策を“設計”することが求められます。
言い換えれば、経営や組織の課題に対して「デザインする」視点が欠かせないのです。新商品の開発支援でも、新たな事業の立ち上げでも、必ず求められるのはユーザー中心の発想と小さな実験の繰り返しであり、まさしくデザイン思考のプロセスと一致します。ファッション業界から始まり、さまざまな業界へ飛び込む中で培った“デザインする”力は、今やどのような業種のクライアントに対しても応用できる共通言語になりました。
こうした経験を通じて実感しているのは、「デザイン思考」は特定のデザイナーやクリエイターだけのものではなく、経営者やコンサルタント、あるいは技術者やサービス業など、あらゆる人が取り入れることで大きな成果を得られる普遍的な思考フレームワークだということです。
────────────────────────
3. デザイン思考の5段階プロセス概要
────────────
では、いわゆる「デザイン思考」と呼ばれる考え方は、具体的にどのようなステップで進むのでしょうか。さまざまなバリエーションがありますが、代表的な整理として5つの段階を紹介します。実際には前後に行き来しながら進めることも多い点にご注意ください。
3-1. 共感(Empathize)
まずはユーザーや顧客、あるいは現場の当事者を深く理解するステップから始まります。ファッションから飲食まで私が関わってきたどの事業でも、顧客インタビューや観察、時には自分自身が顧客と同じ体験をしてみるなど、多様な角度から「利用者の本音」を探ることが重要でした。表面的なアンケート結果だけでなく、行動の背景や文脈を理解することが鍵です。
3-2. 定義(Define)
共感を通じて得た情報を整理し、核心となる問題やニーズを言語化していく段階です。建築の例で言えば、「見た目のデザインだけではなく、居住者の動線やライフスタイルに合わせて空間を最適化する必要がある」といった形で、真の課題をクリアにする作業に近いでしょう。ファッションなら「特定のシーンで使いやすい機能を求めているが、市場にはまだ適切な商品がない」と問題を定義するイメージです。
3-3. アイデア創出(Ideate)
定義した問題に対して、可能な限り多くの解決策を考え出します。ここでは一気に思考を広げ、「通常なら突飛だと思うようなアイデア」も含めてブレインストーミングを行うのがポイントです。ファッションの企画会議でも、まずは「予算や技術的制約を気にせずに理想の形を描いてみる」ことを推奨していました。後から絞り込むとしても、最初は視野を制限しないほうが、ユニークなアイデアが浮かびやすいのです。
3-4. 試作(Prototype)
有力なアイデアを選び、実際に試作品やモデルを作るプロセスです。アパレルならサンプルウェアを製作し、飲食ならメニューの試作、エステなら実際の施術プランのモニタリング、建築なら簡易的な模型や3Dモデルを作るなどが該当します。経営コンサルの場面でも、新サービスのプロトタイピングや小規模な実証実験を設計し、実際に試してみることが重要になります。
3-5. テスト(Test)
プロトタイプを実際のユーザーや顧客に触れてもらい、感想や反応を収集する段階です。その結果を踏まえて改良したり、場合によっては問題定義のステップに戻ることもあります。私自身、飲食店の新メニューを試作し、スタッフや常連客の声を聞きながら少しずつメニューのバリエーションを調整していくことを繰り返しました。こうした柔軟なフィードバックループが、最終的に質の高い商品やサービスを生み出してくれます。
────────────────────────
4. デザイン思考の特徴と利点
────────────
4-1. 人間中心のアプローチ
ファッションや飲食、建築など、どれだけ分野が異なっていても「人を中心に考える」という点は共通しています。デザイン思考では、企業の都合や生産効率を優先するのではなく、まずは誰のどんな悩みを解決するのかを探るところからスタートします。サービス利用者にとって本当に必要とされるものを提供しようとする姿勢が、結果としてビジネスを成長させる土台になるのです。
4-2. 反復的(イテレーティブ)なプロセス
私はこれまで、さまざまな事業領域で何度も試作と改善を繰り返してきました。服のサンプルを作っては修正し、店舗の内装を変更しては反応を確かめる。デザイン思考では、共感→定義→アイデア→試作→テストというステップを何度も行き来しながら、少しずつ理想的な形を磨いていきます。初期段階で完璧を求めずに、むしろ素早く“失敗”を積み重ねることで大きな成功に繋げられる考え方です。
4-3. 失敗を許容する文化と迅速な学習
新しいメニューを開発する時も、思い通りにいかず在庫を抱えてしまった時も、そこから学んだことが次の成功の種になる――という経験を、私は何度も味わいました。デザイン思考は、そうした失敗を“最小限のコストで素早く学ぶ機会”として捉えます。一般的に日本企業では失敗を避ける傾向があると指摘されますが、不確実性の高い時代こそ、失敗から得る洞察が非常に重要です。
4-4. 多様性とコラボレーションの重視
ファッションの世界でも、デザイナー・パタンナー・縫製工場・販売スタッフ・広報担当など多様な役割の人が関わります。建築なら、設計者だけでなく施工業者や設備会社、施主(クライアント)の意見をまとめる必要がある。異なる視点を持つ人たちが協力することで、新たなアイデアや改善点が見えてきます。デザイン思考は「一人の天才がすべてを決める」のではなく、多様なチームが協働しながらユーザーのためのベストを模索するプロセスでもあるのです。
────────────────────────
5. なぜ今、デザイン思考が注目されるのか
────────────
5-1. VUCAの時代への適応
現代はVUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代と呼ばれ、先を読んで長期的な計画を立てることが難しくなっています。ファッション業界もトレンドの移り変わりが激しく、飲食業も顧客の嗜好が急速に変わる可能性があります。そんな時代には、デザイン思考の「小さく試して学びを得る」というアジリティ(俊敏性)が大いに役立ちます。
5-2. イノベーションを生む組織文化
デザイン思考を取り入れると、社員やチームがユーザーの声を積極的に拾い、新しいアイデアを恐れず実行する風土が育ちます。ファッションビジネスや外食産業など、常に新作を打ち出し続けるような世界では、試行錯誤を短いサイクルで回す文化が根付いていると強いです。結果として、イノベーションの種を日常的に生み出す土台が整います。
5-3. サービス・商品開発だけでなく社会課題解決にも
デザイン思考は民間のビジネスだけでなく、行政サービスや地域活性化などの社会課題にも応用できます。ユーザー(市民や地域住民など)の声を深く共感的に聴き、少しずつ試行錯誤を進めながら解決策を探るアプローチは、どの分野にも通じるものだからです。複雑な課題に対しても、多様なステークホルダーを巻き込みながらプロトタイプを重ねることで、新たな打開策が生まれる可能性が高まります。
────────────────────────
6. デザイン思考を活用した事例の概略
────────────
6-1. 大企業での新規事業創出
デザイン思考が注目されるようになった背景には、大企業がイノベーションを求めて採用するケースが増えたことが挙げられます。例えば、エレクトロニクスメーカーが新たなヘルスケア関連サービスを開発する際に、ユーザーインタビューや観察から潜在ニーズを洗い出し、実証実験を通じて機能を磨き上げていく――これこそがデザイン思考の典型例といえます。
6-2. スタートアップの素早いプロトタイプ開発
リソースの限られたスタートアップにとっては、「無駄な投資を避けながらアイデアの検証を高速で回す」ことが死活問題です。デザイン思考は、早い段階で試作品をユーザーに使ってもらい、そのリアルな反応から学ぶことを推奨します。これは私がファッションブランドを立ち上げる時に、最初から大量生産をせず、小ロットでサンプルを作ってテスト販売し、顧客の反応を見てから増産を決める――という手法とも通じています。
6-3. 社会課題へのアプローチ
例えば、地方創生やコミュニティ再生の分野でも、住民とのワークショップを開き、意見を引き出しながらプロトタイプ的にイベントを企画する。そこから得られた気づきを次の施策に反映し、徐々に町全体の活性化につなげていく事例が各地で報告されています。私自身も建築や街づくりの相談を受ける際には、まずその地域の人々と「共感」を深めることが欠かせないと感じています。
────────────────────────
7. さらに一歩先を行くデザイン思考のポイント
────────────
ここまでは、デザイン思考の基礎的なフレームワークと特徴を整理してきました。私がファッションから始まり、エステ、飲食、建築、そして経営コンサルに至るまで、この考え方に支えられてきたことを強く実感しています。最後に、もう少し先を見据えた視点をいくつか挙げてみましょう。
7-1. アナリティクスやAIとの組み合わせ
ビッグデータやAI(Artificial Intelligence)の活用が進む中、ユーザー行動の定量データを分析して仮説を立て、その仮説をデザイン思考のプロセス(共感やテスト)で検証する――という連携が非常に有効です。ファッションのトレンド予測ではSNSデータを分析し、飲食店の集客ではPOS(販売時点情報管理)データを活用するなど、デジタル技術と“人間中心の視点”を組み合わせることで、より高い精度で顧客体験をデザインできるようになります。
7-2. サステナブルデザインへの応用
近年、環境負荷の軽減や社会的課題への配慮がビジネスの必須要件になりつつあります。ファッションではエシカル素材の活用や廃棄ロス問題、飲食では食品ロスや地産地消といったテーマが注目されています。デザイン思考を使う際に、「ユーザー」だけでなく「環境」や「コミュニティ」といった要素をステークホルダーとして捉えることで、持続可能な解決策を創造できる可能性が高まります。
7-3. 組織全体を巻き込むトランスフォーメーション
デザイン思考を部分的に導入するだけでは効果が限られてしまうケースがあります。トップマネジメントから現場スタッフまで、共通言語として「ユーザー視点」「試行錯誤」「失敗の許容度」を高めていく組織づくりが重要です。私が経営コンサルタントとして感じているのは、ファッションブランドでも他業種でも、社内全体でデザイン思考を共有できた時に、はじめて真のイノベーションが生まれるということです。
────────────────────────
8. まとめと次回予告
────────────
ここまで、私がファッション業界からスタートし、エステサロンや飲食、建築など多岐にわたる事業を経営してきた経験を踏まえながら、「デザイン思考」とは何かを整理してきました。振り返ると、どの業界においても「利用者や顧客に寄り添い、課題やニーズを丁寧に汲み取り、試行錯誤を繰り返してサービスや商品を磨く」という姿勢こそがビジネス成功の鍵になっていたと実感します。
改めて、デザイン思考の要点をまとめると
• ユーザー(顧客、当事者)を中心に据え、深い共感から課題を見つける
• アイデアを豊富に出し、プロトタイプとテストを素早く回して学習する
• 失敗を許容し、チームでコラボレーションしながらイノベーションを起こす
• サステナブルな視点やAI活用などと組み合わせ、さらに次の段階へ
という流れになります。そして何より、デザイン思考は決して「デザイナーだけのもの」ではなく、経営やサービス、社会課題解決など、幅広い場面で役立つ共通言語だということを強調したいです。私自身が実際に多業種に携われた理由も、まさにこの“人間中心のアプローチ”があったからこそだと思います。
次回(第2回)では、デザイン思考の最初のステップである「共感(Empathize)」を深く掘り下げます。ファッションでも飲食でも、あるいは建築でも、ユーザーの立場や感情をどのように理解し、そこから洞察を得るかが最重要課題です。具体的なインタビュー手法や観察のコツ、体験共有の方法などを詳しく紹介していきますので、ぜひお楽しみに。
────────────────────────
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。私が複数の業界にまたがってビジネスを手掛けられた背景には、常に「顧客や利用者を深く理解し、解決策をデザインする」という姿勢がありました。その核となるデザイン思考は、現代の不確実な時代にこそ多くのヒントを与えてくれます。
次回は、まさにデザイン思考の出発点である「共感」にフォーカスします。共感がなければ、どんなアイデアも現実からかけ離れたものになってしまうからです。ぜひ次回もご期待ください。