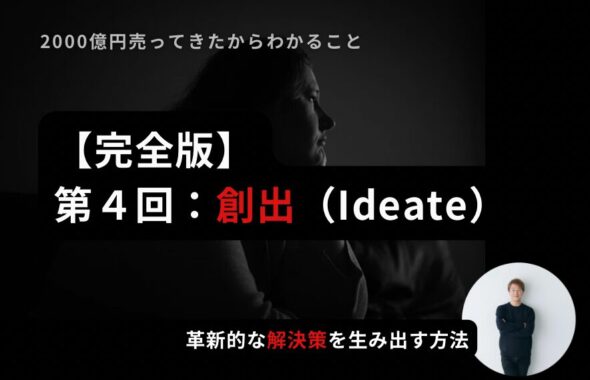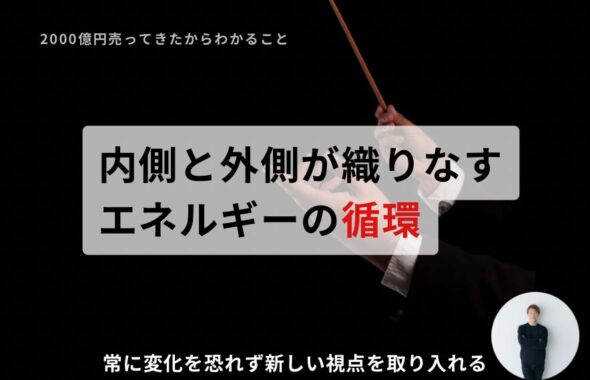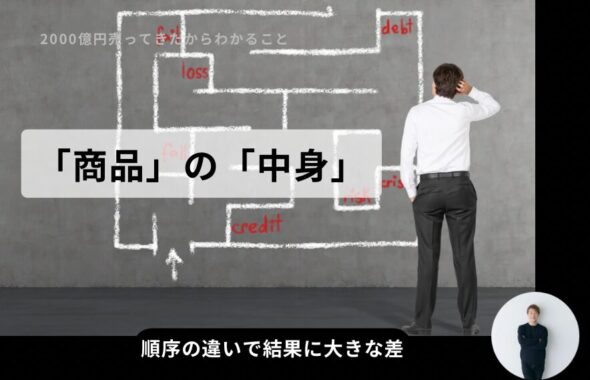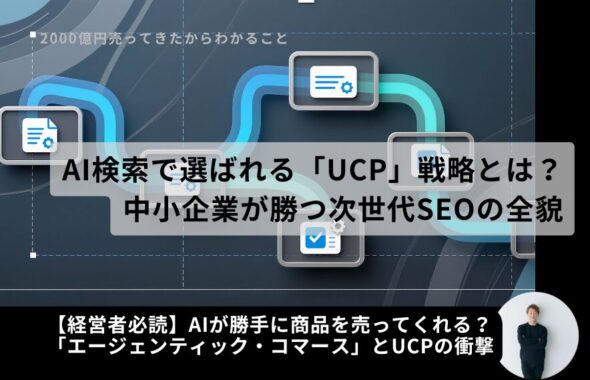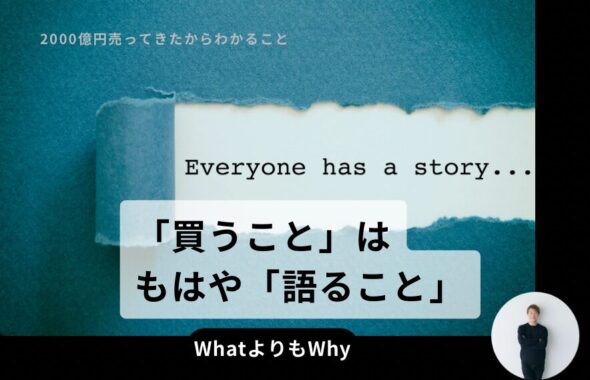第2回:共感(Empathize)の力|中小企業経営に活かす顧客理解
Contents
ユーザー視点を理解する第一歩
1. はじめに
────────────
こんにちは!デザイン思考を5つのステップに分けて解説するシリーズの第2回目は、最初のステップである「共感(Empathize)」にフォーカスします。デザイン思考では、ユーザーや顧客、あるいは地域住民など当事者の視点を深く理解するプロセスを最優先に据えます。私自身、ファッション業界や飲食事業、コンサルティングなど様々な領域で事業を手掛けてきましたが、どの業種でも「最終的に重要なのはどれだけユーザーを理解できたか」という事実は変わりません。
データやアンケート調査によってユーザー情報を得ることは一般的ですが、それだけで本当のニーズを捉えるのは難しい場合が多いです。ユーザー本人ですら言葉にできない、あるいは意識していない課題や不満が潜んでいることが往々にしてあるからです。そうした「隠れたニーズ」や「本質的な課題」を浮き彫りにするために役立つのが、この「共感(Empathize)」のステップです。
今回の記事では、共感とは何なのか、その重要性、具体的なリサーチ手法、そしてビジネスの現場でどのように活用されているかを解説します。さらに、私自身がファッションや飲食といった事業でどのようにユーザーの声を引き出し、新たなアイデアにつなげてきたかといった実践例もお話しできればと思います。ぜひ最後までお付き合いください。
────────────────────────
2. 共感(Empathize)とは何か?
────────────
2-1. デザイン思考における共感の位置づけ
デザイン思考には「共感 → 定義 → アイデア創出 → 試作 → テスト」という5つの段階がありますが、その中でも「共感」は最初に位置づけられています。ここでいう「共感(Empathize)」とは、ユーザーが感じていること、考えていること、行動している理由などをできる限り深く理解するプロセスです。いわゆるアンケートや統計データの分析も有用ですが、それだけでは本質に届かないことが多々あります。ユーザーの感情や背景、状況を丁寧に把握するために観察・インタビュー・体験などを組み合わせることが重要です。
2-2. 「ユーザーの本音」に迫るためのプロセス
私がファッションブランドを経営していた時代にも、顧客のデータやSNSの反応をチェックしていましたが、それだけでは「どうしてその服を着たいのか」まで突き止められないことを痛感していました。実際にお客様と会話し、販売スタッフのフィードバックを聞き、時には自分自身がその顧客層の生活スタイルを体験してみることで、本当のニーズを見出せたことを何度も経験しています。
「共感」フェーズで得られるユーザー像や課題感は、その後の「定義」「アイデア創出」の土台となります。最初のステップを疎かにしてしまうと、表面的な問題解決に留まったり、ユーザーの心を打たないアイデアを量産してしまうリスクが高まります。だからこそ、デザイン思考の全体フローにおいて「共感」がきわめて重要な要素となるわけです。
────────────────────────
3. 共感がもたらす3つの価値
────────────
3-1. 隠れたニーズの発見
ユーザー自身が意識していない、本当に求めている価値や解決策は意外に多いものです。例えば、ある顧客が「もっと手早く移動したい」と言ったからといって、ただ速い車を提供しても満足しない場合があります。実際には「移動時間を減らして家族と過ごしたい」と考えているのであれば、車ではなく別の手段が適切になるかもしれません。共感のプロセスでは、こういった「実はユーザーが真に求めているもの」を炙り出しやすくなります。
3-2. ユーザー視点での課題再定義
ビジネス側から見た課題と、ユーザーが抱える課題は必ずしも一致しません。私自身、飲食店を立ち上げる際に「客席の回転率を上げるにはどうすればいいか?」と考えがちでしたが、実はユーザーは「ゆったり落ち着ける空間で食事がしたい」と思っていた。もしユーザー目線をしっかり理解していなかったら、店のレイアウトやサービス内容が真逆の方向に向かってしまう可能性があったでしょう。共感によってユーザー視点の課題を的確に定義することで、解決策の質が大きく向上します。
3-3. イノベーションの種を見つける
革新的なアイデアは、多くの場合ユーザーの「困りごと」や「不満」から生まれます。特に、ユーザーも言語化できていない不満や不便が埋まっている領域ほど、事業機会やイノベーションの可能性は大きいです。私が経営コンサルタントとしてクライアント企業をサポートしているときも、社員や顧客へのインタビューを通じて小さな不満の積み重ねを紐解き、そこから新サービスが生まれたケースを何度も目撃してきました。
────────────────────────
4. 共感プロセスで使える手法
────────────
共感フェーズでは、実際にユーザーと接点を持ち、感情や行動の裏側を理解するためのさまざまなアプローチが存在します。ここでは代表的な4つの手法を紹介します。
4-1. 観察(Observation)
ユーザーの日常生活や行動を客観的に観察して、どんな状況で何に困っているか、どんな工夫をしているかを把握する方法です。ファッションブランド経営時代には、店舗でのお客様の動きをスタッフと共に観察し、「試着する前に商品タグを細かくチェックする人が多い」「特定コーナーで足を止めやすい」などの行動パターンを発見することができました。飲食店でも、注文のタイミングや席を選ぶ傾向を観察すると、レイアウトやオペレーション改善のヒントが得られます。
観察で重要なのは、できるだけ“意識されていない行動”に注目することです。ユーザーは言葉にはしないが、実は困っている、あるいは工夫しているシーンが潜んでいます。そこを見逃さないように、先入観を持たずに観察する目が必要です。
例:スーパーでの買い物行動の観察
小売の世界では、顧客が商品棚の前でどのくらい立ち止まり、どんな商品に興味を示すかを実際に観察することで、「棚の高さが合っておらず、特定の層には取りづらい」とか「主力商品が陳列場所的に目立ちにくい」など、課題を可視化できます。私自身、飲食店のメニューを「どの位置に置くか」でも売れ行きに大きな差が出ることを観察して学びました。
4-2. インタビュー(Interview)
直接ユーザーに質問することで、考え方や感情を深く掘り下げます。ここで大切なのは、単なるアンケートのように定型化された質問ではなく、オープンエンドの質問を投げかけることです。「この製品はどうですか?」ではなく「最近、〇〇について困った経験はありますか?」のように、相手が自由に語れる余地を残す質問が効果的です。
有効な質問例
• 「普段どんなシーンでこのサービスを使いますか?」
• 「最近、大変だったことや不安に思ったことを教えてください」
• 「もし何でも自由にできるとしたら、どんな改善を望みますか?」
インタビュー時には声のトーンや表情、言葉に詰まったタイミングなど非言語的な情報も要チェック。ユーザーが言い淀んだ部分にこそ本音や隠れたニーズがある場合が多いです。
4-3. 体験(Immersion)
ユーザーと同じ体験をしてみる手法です。私が飲食店を立ち上げる時は、自分自身でお客さんの立場になって同じ導線を使ってみました。入口から入ってテーブルに着くまでのスムーズさ、スタッフとのやりとりのしやすさ、注文の際のストレス度などを自分の体感として把握することで、机上のプランでは見えてこない改善点がいくつも見つかります。
例:車椅子生活者の施設利用体験
建築分野では有名な例ですが、設計者が車椅子を使った生活を実際に体験することで、段差やドア幅、トイレ設備などの問題に気づくケースがあります。ユーザー本人の視点と設計者の視点では大きな差があるため、こうした“体験”による共感がデザインを大きく進化させます。
4-4. エンパシーマップ(Empathy Map)
観察やインタビュー、体験で得た情報を「言っていること(Says)」「していること(Does)」「考えていること(Thinks)」「感じていること(Feels)」の4つに仕分けて整理する手法です。可視化することで、ユーザーの行動と感情、発言の矛盾点や隠された意図を読み取りやすくなります。私もコンサルの場面でクライアント先にエンパシーマップを導入し、チーム全員でユーザー像を共有することで、共通認識が格段に高まった経験があります。
────────────────────────
5. ビジネス現場での共感活用例
────────────
このラインより下のエリアがnoteでは有料で表示されます。
5-1. Airbnb:創業者がユーザー自身になる
Airbnbの創業者たちは、サービス立ち上げ当初、自分たちがホストとなって実際に部屋を貸し出し、また別のホストの部屋に泊まる経験を積みました。ホストとゲスト、双方の視点を深く理解したことで、「予約時の不安」「到着後の戸惑い」「部屋探しの難しさ」などリアルな課題が見えてきたのです。こうして得た洞察がサービス全体のUI/UX(User Interface/User Experience)や口コミ機能の設計に反映され、Airbnbは急速に利用者を拡大していきました。
5-2. P&G:スタッフが当事者体験を積む
P&Gは新しいおむつを開発するとき、母親へのインタビューだけでなく、スタッフ自身が赤ちゃん人形を使っておむつ交換を体験し、さらには夜中にも起きて交換を行うという擬似生活を行いました。これによって「夜中でも簡単に替えられる構造」「赤ちゃんの肌への刺激を最小化する素材選び」などの着想を得ることができ、大ヒット商品へと繋がったという事例があります。共感は机上のデータだけでなく、実際に動いてみることで深まる典型例です。
────────────────────────
6. 共感プロセス成功へのポイント
────────────
では、こうした共感フェーズを効果的に実践するにはどのような点に気をつけるべきでしょうか。以下の3つは、私が自身の事業経験やコンサル活動を通じて特に大切だと感じているポイントです。
6-1. 先入観を捨てる
「顧客はきっと〇〇を望んでいるだろう」「このサービスは使いづらいに決まっている」などの先入観や思い込みを持ってしまうと、ユーザーの本音に届きにくくなります。共感を得る過程では、「自分たちの予測が間違っているかもしれない」という姿勢で臨むことが重要です。ファッション時代、私も「この色は絶対売れる」と信じ込んでいた商品が、実際は使いづらいと敬遠されていた経験があります。ユーザーとの対話を積み重ねた結果、サイズやシルエットで不満が生まれていたことを知り、そこを改良することで売れ筋に変化した事例もありました。
6-2. 多様な手法を組み合わせる
観察だけ、インタビューだけでは偏った情報になりがちです。観察で気づいた点をインタビューで深掘りし、インタビューで生まれた疑問を体験を通じて検証するなど、複数の手法を組み合わせることで理解が一層深まります。私が飲食店を開業するときは、初期段階で来店客の様子を観察し、スタッフと一緒にインタビューを行い、さらに自分が客として入店してみるなどして多角的に情報を得ました。
6-3. チーム全員で取り組む
デザイン思考のプロセスは個人プレーではなく、チームで協力することで成果が最大化します。例えば、ファッションビジネスではデザイナー、パタンナー、販売スタッフ、マーケティング担当など異なる職種のメンバーが連携すると、新たな気づきが出やすくなります。コンサルティングの場面でも、プロジェクトチームがユーザーへの共感を共有することで、意図がズレた施策に進みにくくなるメリットがあります。
────────────────────────
7. 私自身の事業経験における「共感」の実践
────────────
ここでは、私がさまざまな業界で事業を手掛けてきた中で、特に印象深かった「共感」のエピソードをいくつか紹介します。
7-1. ファッションブランド経営時代:顧客の暮らしを想像する
ファッションブランドの企画・販売を行う際、単に「このデザインが流行るだろう」と考えるのではなく、「どのようなライフスタイルの人が、どんなシーンでこの服を着るのか?」を具体的に想像するようにしていました。20代のアクティブな女性が昼休みにカフェへ行くとき、夜に友人と食事をするとき、どんな気分を求めているのか――そうしたストーリーを頭に描いてスタッフと議論する。時にはお客様と直接会話し、どのようなきっかけで洋服を選ぶのかをヒアリングしてみる。そうすることで、単なる商品機能ではなく「感情面の満足」を提供できるデザインにたどり着くことができました。
7-2. 飲食事業でのメニュー開発:現場観察から気づくこと
飲食店を立ち上げたとき、特に力を入れたのがメニュー開発です。最初は「おしゃれで映える料理」に注目しがちでしたが、実際に店舗に立ってお客様の反応を観察していると、「注文してから提供されるまでの待ち時間が長い」「メニュー名がわかりづらい」という声を聞くようになりました。そこで、調理工程を見直し、メニュー構成をシンプルにし、商品名にも分かりやすい補足説明を加えることで顧客満足度が向上しました。これはまさに共感を得ることで本当の課題が分かり、解決策につながった好例です。
7-3. コンサルタントとしてのヒアリング:隠れた本音に迫る
経営コンサルタントとしてクライアント企業のプロジェクトを進める際、必ず行うのが「現場ヒアリング」と「顧客インタビュー」です。例えば建築業界のクライアントが新事業を検討していたとき、施工担当者や設計士だけでなく、依頼主や利用者の声をじっくり聞くことで、最終的に「省エネ志向だがデザイン性も求める」というニーズのバランスが判明しました。そこを軸にプロトタイプを設計していくことで、競合との差別化にも成功しました。こうした「真のニーズ」は、観察とインタビュー、体験を通じて初めて明確になるケースが多いのです。
────────────────────────
8. まとめと次回予告
────────────
デザイン思考の第2回目として、「共感(Empathize)」について詳細をお伝えしました。共感とは、ユーザーが何を感じ、考え、どのような状況に置かれているのかを深く理解するプロセスです。これを徹底して行うことで、表面的には見えない課題やニーズを発見でき、結果的にイノベーションの源泉にもなります。
主なポイントを振り返ると次のとおりです。
• 共感が重要な理由:隠れたニーズの発見、ユーザー視点の課題再定義、イノベーション創出
• 具体的な手法:観察、インタビュー、体験、エンパシーマップなど
• 成功のポイント:先入観を捨てる、多様な手法を組み合わせる、チーム全員で取り組む
• 実践例:Airbnbの両サイド体験、P&Gのおむつ開発、私自身のファッションや飲食事業、コンサルでの活用
私はこれまで多くの業種でビジネスに取り組んできましたが、どの領域においても「顧客の視点に立つ」という姿勢が成果の大半を決めると感じています。共感がなければ的外れなサービスや商品を作り続ける危険性が高まり、逆に共感がしっかりできれば業界を超えた発想転換や新規事業のチャンスも見えてくるのです。
次回(第3回)は、共感フェーズで得た情報をどう整理して、デザイン思考の次のステップである「定義(Define)」につなげるかを解説します。正しく問題を定義することが、その後のアイデア創出やプロトタイプの方向性を大きく左右しますので、非常に重要なステージです。ぜひお楽しみに。
────────────────────────
(約10,000文字)
ここまでお読みいただきありがとうございました。デザイン思考の入り口である「共感」は、一見回り道のように思えるかもしれませんが、ここを丁寧に行うことで後のプロセスがスムーズに進み、結果として短期間で本質的な課題解決に到達しやすくなります。ファッション、飲食、建築など、どの分野でも私が実感してきた「ユーザー目線の大切さ」を、ぜひ皆さんの取り組みにも活かしていただければ幸いです。
それでは次回、ユーザー情報をどうやって「定義(Define)」へと昇華させるのか、一緒に学んでいきましょう。