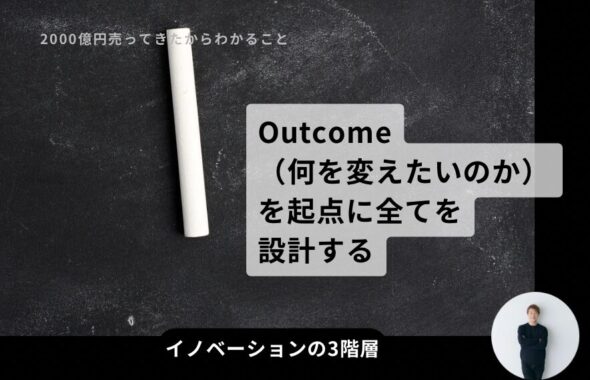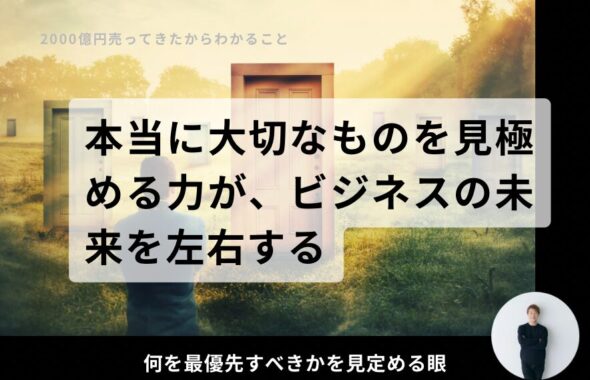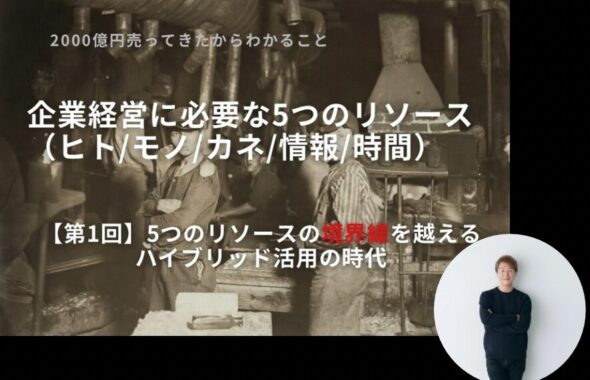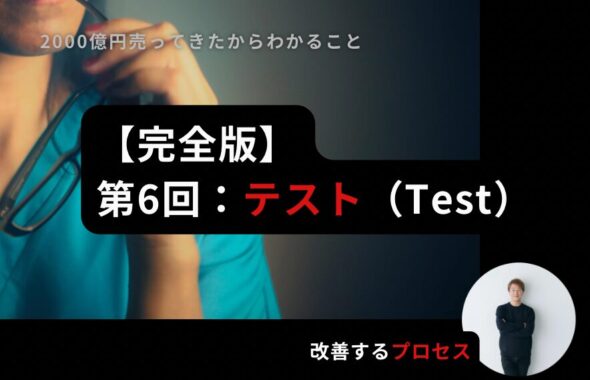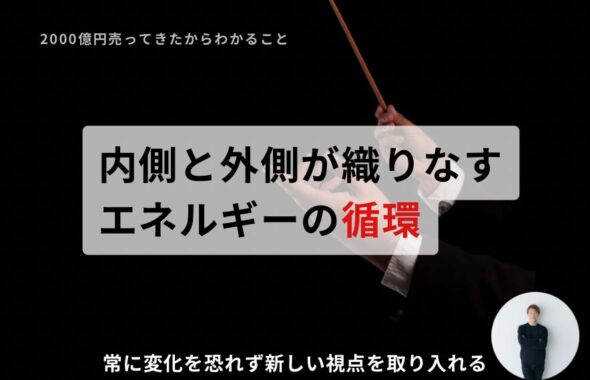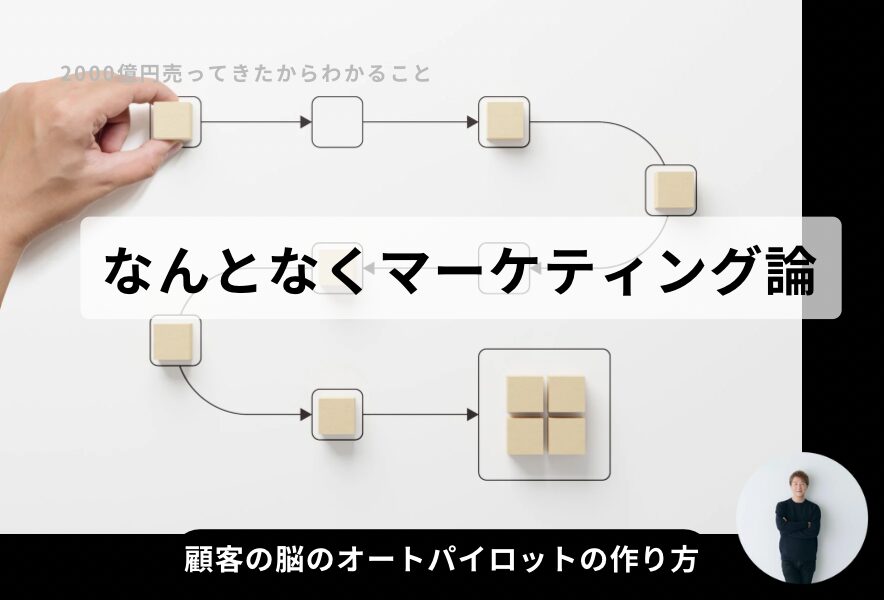
「なんとなく」の力:顧客が思わず選んでしまう、直感的なブランドの作り方
Contents
「なんとなく」の力:顧客が思わず選んでしまう、直感的なブランドの作り方
論理と価格を超えて存在する「なんとなく」という隠れた力
自社の製品は完璧で、価格も競争力がある。それにもかかわらず、顧客が店の前を通り過ぎたり、ウェブサイトをスクロールして競合他社を選んだりする光景を目の当たりにしたことはないでしょうか。その理由を尋ねても、本人すら明確に説明できず、「なんとなく、そっちの方が気になったから」と答えることがほとんどです。この「なんとなく」という感覚こそ、ビジネスにおいて最も見過ごされがちでありながら、最も強力な影響力を持つ要素なのです。
多くの企業は、価格や機能といった論理的な訴求に注力します。しかし、これらは容易に模倣されてしまいます。真の競争優位性は、顧客の直感的で感情的な選択、つまり「なんとなく」の領域で勝利することにあります。この一見すると不可解な現象は、単なる運や偶然ではありません。それは、戦略的に育て上げることができる、予測可能な心理的メカニズムの結果なのです。
本稿では、この「なんとなく」の選択を、私が提唱する「なんとなくマーケティング」の視点から徹底的に解明します。まず、人間の脳がどのように「自動操縦(オートパイロット)」で意思決定を下すのか、その科学的背景を平易に解説します。次に、その知見を基に、顧客の直感的な第一候補となるブランドを構築するための戦略的設計図を提示します。最後に、中小企業が今日からでも実践できる、低コストかつ効果的な戦術と、それを体現する日本の成功事例を紹介します。この「なんとなくマーケティング」を実践し、顧客の直感を味方につけることで、価格競争から脱却し、持続可能な成長を実現する道筋が見えてくるはずです。
第1章:オートパイロット・ブレイン:「なんとなく」の購買を科学する
1.1 顧客の頭の中の二人:分析的な「パイロット」と直感的な「オートパイロット」
顧客の脳内には、意思決定を司る二つの異なる思考システムが存在します。行動経済学ではこれを「システム1」と「システム2」と呼びますが、ここではより分かりやすく、慎重に分析する「パイロット」と、素早く直感的に判断する「オートパイロット」という比喩で説明します。
パイロット(システム2):
これは、時間をかけて意識的に働く「遅い思考」で、論理的な推論や証拠に基づいて判断を下す、分析的な思考システムです。複雑な計算をしたり、製品のスペックを詳細に比較検討したり、人生の重要な決断を下す際に活動します。パイロットは非常に有能ですが、稼働させるには多くの精神的エネルギーを必要とし、疲れやすいという特徴があります。多くの企業が、顧客のこの「パイロット」に対して一生懸命に製品の優位性を説こうとします。
オートパイロット(システム1):
こちらが今回の主役です。オートパイロットは、素早く自動的に働く「速い思考」で、無意識的に作動します。個人の経験則や直感、感情に基づいて、ほとんど努力を必要とせずに物事を判断します。ただし、深く考えずに判断するため、バイアス(思い込み)や誤りが生じやすいという側面も持っています。日常生活における意思決定の大部分、その中には購買行動の多くも含まれますが、これらはオートパイロットによって下されています。顧客が口にする「なんとなく」という感覚は、まさにこのオートパイロットが発するシグナルなのです。
人間の脳は、生存本能としてエネルギー消費を最小限に抑えようとプログラムされています。そのため、日常的な判断のたびに分析的な「パイロット」を起動させるのは、精神的なマラソンを強いるようなものです。顧客は無意識のうちに、そのような認知的な負荷を避けようとします。選択肢が多すぎたり、情報が複雑だったりすると、顧客は精神的なストレスを感じます。逆に、馴染みがあり、信頼でき、理解しやすいブランドは「認知的な容易さ」をもたらし、オートパイロットはこれを「正しい選択」というポジティブな感覚として解釈します。したがって、「なんとなくマーケティング」の目標は、パイロットを論理で説得することではなく、オートパイロットに直感的な安心感を与えることにあるのです。
1.2 オートパイロットの判断基準:「なんとなく」を引き起こす3つの心理的ショートカット
オートパイロットは、迅速な判断を下すために、いくつかの経験則、つまり心理的なショートカットを利用します。このショートカットを理解し、戦略的に活用することこそが、「なんとなくマーケティング」の鍵となります。
ショートカット1:社会的証明(「みんなが買っているなら、良いものに違いない」)
人間は、集団の中で行動することでリスクを避けるように進化してきました。そのため、他者の選択に強く影響されます。これは「同調習性」や「バンドワゴン効果」として知られています。多くの人が支持している、あるいは流行しているという事実は、オートパイロットにとって「この選択は安全で、すでに多くの人によって検証済みだ」という強力なシグナルとなります。これが、「売上No.1」という表示や、SNSでの多くの好意的な口コミ、インフルエンサーのおすすめが絶大な効果を発揮する理由です。これらは、顧客が自ら時間と労力をかけて評価する必要をなくし、選択を正当化する手助けをします。
ショートカット2:感情のタグ付け(「これは、心地よい/安心/特別な気分にさせてくれる」)
オートパイロットは、製品の仕様書ではなく、感情を読み取ります。購買行動は、ストレスからの解放、幸福感、自己実現といった感情と密接に結びついています。例えば、「このアロマキャンドルを使えば、リラックスできる空間が手に入る」といった期待感は、製品の機能そのものよりも強力な購買動機となり得ます。企業の創業ストーリーや製品開発の背景にある物語は、こうした感情的なタグを顧客の心に深く刻み込むための強力なツールです。オートパイロットは、データではなく物語に引き寄せられるのです。
ショートカット3:親近性の原理(「このブランドは知っているから、信頼できる」)
オートパイロットは、未知のものをリスクとみなし、既知のものを安全と判断する傾向があります。これは「省略習性」とも関連しており、消費者は毎回ゼロから選択肢を評価するのではなく、あらかじめ記憶の中にある馴染み深いブランドに頼ることで、選択のコストを省略します。特に、継続的に購入する商品カテゴリーではこの傾向が顕著です。広告やパッケージ、SNSなどを通じて一貫したメッセージに繰り返し触れることで、ブランドは単なる認知度を超え、「親近性」を獲得します。この親近性こそが、オートパイロットにとっての「信頼」の証となるのです。
第2章:「なんとなく」選ばれる存在へ:オートパイロットに響くブランド構築
2.1 ブランドとは、オートパイロットへの「約束」である
システム1の文脈でブランドを再定義すると、それは単なるロゴや名称ではありません。ブランドとは、顧客の記憶の中に蓄積された、感情、経験、期待の集合体です。それは、オートパイロットが混雑した市場の中で迅速かつ自信を持って意思決定を下すための、強力な心理的ショートカットなのです。
強力なブランドは、顧客が購買時に感じる様々なリスクを低減させる「約束」として機能します。ケビン・レーン・ケラー教授が示すように、顧客は購買時に少なくとも6つのリスクを感じています。
- 機能的リスク:期待した性能を発揮しないかもしれない。
- 身体的リスク:健康や安全を害するかもしれない。
- 金銭的リスク:支払った価格に見合う価値がないかもしれない。
- 社会的リスク:これを選ぶことで、他人から悪く思われるかもしれない。
- 心理的リスク:これを選ぶことで、自己イメージが損なわれるかもしれない。
- 時間的リスク:選択を誤り、再検討する時間を無駄にするかもしれない。
信頼できるブランドは、これらのリスクに対して「この選択で後悔はさせません」という暗黙の保証を与えます。これこそ、リスクを避けたいオートパイロットが最も求めているメッセージなのです。例えば、旅先で見慣れないカフェが並ぶ中で、スターバックスを見つけると「なんとなく」入ってしまうのは、味が保証され、店の雰囲気や価格帯まで予測できるという安心感、つまり探索コストの低減とリスク回避が働いているからです。
2.2 「なんとなく」選ばれるブランドがもたらす、確固たる経営基盤
「なんとなくマーケティング」を通じて直感的に選ばれるブランドを構築することは、単なるイメージ戦略ではなく、企業の収益性と持続可能性に直結する経営戦略です。
メリット1:価格競争からの脱却
「なんとなく」の好意を勝ち得たブランドは、価格の比較対象から外れやすくなります。顧客は単に製品を購入しているのではなく、そのブランドが提供する信頼、感情、自己表現の価値を購入しているため、その確実性に対してプレミアムを支払うことを厭いません。これにより、利益率の高い安定した経営が可能になります。
メリット2:持続可能な競争優位性の構築
競合他社は製品を模倣できても、顧客の心の中に築き上げられた信頼や愛着を模倣することはできません。このブランド・ロイヤルティは、企業の周りに見えない「堀」を築き、市場環境の変化に対する抵抗力を高めます。また、熱心なファンは自発的に口コミを広げてくれるため、高額な広告宣伝費への依存度を下げることができます。
メリット3:優秀な人材の獲得
ポジティブなブランドイメージは、顧客だけでなく、求職者にも魅力的に映ります。その企業で働くことに誇りを持てるため、情熱を持った優秀な人材が集まりやすくなります。採用コストが削減されるだけでなく、エンゲージメントの高い従業員は、結果としてより良い顧客体験を提供し、ブランドをさらに強化するという好循環を生み出します。
これらのメリットは個別に機能するのではなく、相互に作用し、自己強化のループを形成します。強力なブランドがもたらす高い利益は、より良い製品開発や顧客体験への再投資を可能にします。優れた顧客体験は、顧客の信頼とロイヤルティをさらに深め、ブランドを強固なものにします。この好循環、いわば「ブランドの複利効果」を始動させることが、中小企業が大手と伍して戦い、長期的に成長するための鍵となるのです。
2.3 中小企業のためのシンプルなブランド構築設計図
「なんとなくマーケティング」の核心であるブランド構築は、大企業だけのものではありません。以下の3つのステップは、リソースが限られた中小企業でも実践可能な、本質的なアプローチです。
ステップ1:理想の「たった一人」の顧客を定義する(ペルソナの力)
すべての人に好かれようとするブランドは、誰の心にも響きません。最初のステップは、自社が最も届けたい理想の顧客像、つまり「ペルソナ」を具体的に描き出すことです。これは単なる年齢や性別といった人口統計データではありません。その人物の価値観、悩み、喜び、ライフスタイルまでを深く掘り下げた、実在するかのような人物像です。
この「たった一人」を明確にすることで、ブランドの語り口に一貫性が生まれます。ウェブサイトのデザイン、SNSの投稿内容、製品パッケージの色使いまで、あらゆる意思決定の場面で「このペルソナは、これを喜んでくれるだろうか?」という問いが、ブレない判断基準となります。
ステップ2:自社の「なぜ」を発見する(物語の核)
顧客の心を動かすのは、「何を」売っているかではなく、「なぜ」それを売っているかという物語です。自社のビジネスの原点、創業者の情熱、解決したい社会課題など、その背景にあるストーリーこそがブランドの核となります。人は本能的に物語に引き込まれる生き物であり、共感できる物語はブランドに感情的な価値を与え、記憶に深く刻まれます。
ステップ3:ブランドを「体現」する(一貫性の規律)
誰に、何を語るかが決まったら、それをすべての顧客接点で一貫して体現することが不可欠です。製品パッケージ、店舗の雰囲気、ウェブサイト、電話応対、SNSでの言葉遣いなど、顧客がブランドに触れるあらゆる瞬間で、同じ価値観や世界観を感じさせなければなりません。一貫性は、オートパイロットの脳内に親近性と信頼を構築するための最も地道で、しかし最も確実な方法です。矛盾したメッセージは顧客を混乱させ、無意識のレベルで不安やリスクを感じさせてしまいます。
第3章:直感を設計する:「なんとなく」の購買を引き起こす実践戦略
ブランドの設計図が完成したら、次はその設計思想を具体的な顧客体験に落とし込み、「なんとなく」の選択を誘発する仕掛けを施していきます。これこそが、「なんとなくマーケティング」の実践フェーズです。
3.1 第一印象を制する:ネーミング、パッケージ、ビジュアルの力
ネーミング:
製品名は、顧客のオートパイロットが処理する最初の情報です。シンプルで覚えやすく、ポジティブな感情や製品の価値を喚起する名前は、それ自体がマイクロ・ストーリーテリングとなります。思わず口ずさみたくなるような語感の良さも、記憶への定着を助けます。
パッケージデザイン:
パッケージは「棚の上の無言のセールスパーソン」です。店頭やECサイトで顧客が製品に注目する時間はわずか数秒。その一瞬で、色、形、フォント、写真といった視覚要素を通じて、ブランドの核となる価値を直感的に伝えなければなりません。例えば、ジュースブランドのトロピカーナがパッケージデザインを変更した際、トレードマークだった「オレンジにストローが刺さった」イラストをなくしたところ、顧客が棚で製品を認識できなくなり、売上が急落したという有名な失敗事例があります。これは、顧客のオートパイロットが頼りにしていた親しみやすい視覚的ショートカットを奪ってしまったことが原因です。
オートパイロットにとって、あらゆる感覚的な入力は、ブランドの品質と信頼性に関するデータとなります。パッケージの重み、箱を開ける時の音、ラベルのフォント。これらは些細なディテールではなく、ブランドの約束を補強、あるいは毀損する、非言語的な情報なのです。中小企業は、これらの物理的・視覚的資産を単なるコストとしてではなく、顧客の直感に語りかけるための重要な投資として捉えるべきです。少し高価でも、質感の良いパッケージは、そのコストをはるかに上回る価値の知覚を生み出す可能性があるのです。
3.2 「空気感」を創り出す:物理的・デジタル空間の雰囲気
実店舗を持つビジネスの場合:
店舗のデザイン、照明、BGM、香りといった要素は、顧客の感情に直接作用し、ブランドの世界観を五感で体験させます。居心地の良い空間は、顧客の滞在時間を延ばし、購買確率を高めるだけでなく、ブランドに対するポジティブな記憶を形成します。SNSが普及した現代では、写真映えする魅力的な内装は、それ自体が強力な口コミの源泉となります。
すべてのビジネスにとっての「デジタル店舗」:
ウェブサイトは、24時間365日稼働するブランドの顔です。清潔感があり、プロフェッショナルで、直感的に操作できるウェブサイトは、訪問者に瞬時に信頼感を与えます。逆に、情報が煩雑で、表示が遅く、使いにくいサイトは、オートパイロットに「この会社は仕事が雑そうだ」というネガティブな信号を送り、即座に離脱されてしまいます。ここでも重要なのは、シンプルさと分かりやすさです。
3.3 デジタル上の「人格」を育てる:SNSで親近感と好意を醸成する
目的は「転換」ではなく「関係構築」:
中小企業にとってのSNSは、「今すぐ購入」を連呼する広告媒体ではありません。その主な役割は、顧客との関係を築き、親近感を生み出し、ブランドに人間的な温かみを与えることです。
トーン&マナー(語り口の一貫性):
まず、自社ブランドの「人格」を定義します。親切で専門的か、楽しくてユニークか、温かく寄り添う存在か。この人格に基づいたトーン&マナーを、すべての投稿や顧客とのやり取りで一貫させることが重要です。
コミュニティの醸成:
フォロワーに向かって一方的に発信するのではなく、対話を心がけます。コメントに返信し、質問を投げかけ、時にはフォロワーの投稿をシェアする。こうした双方向のコミュニケーションは、受け手だったオーディエンスを能動的なコミュニティの一員へと変え、強力な帰属意識と愛着を生み出します。
第4章:「なんとなく」の例:日本の中小企業成功事例
これまで述べてきたことが企業側の意識・無意識に関わらず、顧客から「なんとなく」選ばれるブランドを築き上げた中小企業の事例を見ていきましょう。これらは、意識的か無意識的かにかかわらず、「なんとなくマーケティング」のわかりやすい例と言えます。それぞれが異なるアプローチで、直感的な選択のトリガーを引くことに成功しています。
4.1 事例:株式会社マーナ — 視覚的一貫性
分析:
マーナは、キッチン、バス、掃除用品といった日用品を製造・販売する企業です。彼らの公式Instagramアカウント(@marna_inc)は、単に製品を紹介する場ではありません。そこには、白を基調とした清潔感あふれる、ミニマルで美しい写真が整然と並び、静かで整った暮らしのイメージが一貫して表現されています。
「なんとなく」のトリガー:
より整理された、美しい暮らしを志向する顧客は、マーナの製品に直感的に惹きつけられます。購入するものはスポンジ一つかもしれませんが、それはマーナのSNSが描き出す理想のライフスタイルを実現するための一歩と感じられます。この徹底された視覚的一貫性が、ブランドの認知度を高め、オートパイロットに「信頼できる、センスの良い選択」という印象を瞬時に与えているのです。
4.2 事例:桐屋旅館 — 感情的結びつき
分析:
長野県野沢温泉にあるこの老舗旅館は、部屋や食事といった一般的な魅力だけでなく、9匹の「看板猫」を前面に押し出したコミュニケーションで際立っています。SNSでは、それぞれの猫の個性や日々の愛らしい行動が、まるで家族を紹介するかのように温かく発信されています。
「なんとなく」のトリガー:
特に猫好きの潜在顧客は、予約する前からこの旅館と猫たちに強い感情的な絆を形成します。宿選びはもはや「旅館A」と「旅館B」の比較ではなく、「一般的な旅館」と「ハチやきなこに会える、あの温かい場所」との選択になります。このユニークで模倣不可能な感情的なフックが、他のあらゆるスペックを凌駕し、「なんとなく、ここがいい」というパーソナルで確固たる選択理由を生み出しています。
4.3 事例:三代目小池精米店 — 物語性
分析:
スーパーマーケットとの厳しい価格競争に直面していた東京・原宿の三代目小池精米店は、リブランディングによって活路を見出しました。全国47都道府県の米の形をモチーフにした美しいロゴを制作し、「全国四十七都道府県のお米と食卓をつなげたい」という理念を可視化しました。さらに、東北6県の米の頭文字をつなげた「あ・さ・ひ・ま・つ・光」のような、物語性のあるギフト商品を開発しました。
「なんとなく」のトリガー:
彼らは「米」というコモディティ(日用品)を、意味のあるギフトや文化的な体験へと昇華させました。顧客が小池精米店を選ぶのは、単に米を買うためではありません。そこには、作り手の情熱や日本の稲作文化を応援するという物語があり、その物語の一部になるという満足感が伴います。この物語的価値が、価格を超えた「なんとなく、ここで買いたい」という強い動機付けとなっているのです。
4.4 事例:菊水産業株式会社 — 「人格」形成
分析:
「つまようじ」という、一見すると差別化が難しい製品を製造するこの企業は、X(旧Twitter)上でユーモアと親しみやすさにあふれた「中の人」のキャラクターを確立し、多くのファンを獲得しています。
「なんとなく」のトリガー:
ありふれた製品に魅力的な「人格」を与えることで、顧客との間に心理的な親近感を築いています。フォロワーが店舗で同社の製品を見かけたとき、オートパイロットは単なる商品ではなく、SNS上で交流のある「友人」を認識します。その選択は簡単で心地よいものになります。なぜなら、その背景には、SNSを通じて育まれたポジティブな感情の蓄積があるからです。
4.1 「なんとなく」戦略マトリックス
これらの事例から、中小企業が「なんとなく」選ばれるための多様な戦略が見えてきます。以下の表は、各社のアプローチを整理したものです。
| 企業名 | 主要な製品・サービス | 中心的な「なんとなく」戦略 | 具体的な戦術例 | 顧客が抱く「なんとなく」の感覚 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社マーナ | 生活雑貨 | 視覚的一貫性と憧れの喚起 | 統一感のあるミニマルなInstagramフィード | 「これを使えば、私の生活も美しく整う」 |
| 桐屋旅館 | 温泉旅館 | 感情的な結びつきと独自性 | 看板猫を中心としたSNSでの物語発信 | 「ここは特別で、心温まる場所だ」 |
| 三代目小池精米店 | 米 | 物語性による価値の昇華 | リブランディングと物語性のある商品開発 | 「本物で、意味のあるものを買っている」 |
| 菊水産業株式会社 | つまようじ | 「人格」形成による親近感 | ユーモアのある人間味あふれるXの運用 | 「この会社は知っているし、好感が持てる」 |
結論:「なんとなく」を、最も予測可能で強力な資産に変える
「なんとなくマーケティング」の視点を通してみると、顧客の「なんとなく、これにした」という言葉は、もはやビジネスにとって不可解な謎ではありません。それは、顧客の脳のオートパイロットが、最も簡単で、最も安全で、最も感情的に響く選択肢を求めた、予測可能な結果なのです。この流れに抗うのではなく、自社がその選択肢そのものになること。それこそが、私が提唱する「なんとなくマーケティング」であり、これからの時代に求められるブランド戦略です。
「なんとなく」選ばれるブランドを築くことは、最も持続可能な競争優位性となります。それは、一夜にして成し遂げられる魔法ではなく、一貫した顧客体験を一つひとつ積み重ねていく、地道で意図的な信頼構築のプロセスです。今日から、自社のビジネスについて、顧客が何を「考えている」かだけでなく、顧客をどんな「気持ちにさせている」かを問い直すことから始めてみてください。
中小企業経営者のための実践チェックリスト
- ペルソナを定義する:自社が本当に喜ばせたい「たった一人」の顧客は誰か?その人物の物語を書き出してみる。
- 自社の「なぜ」を見つける:自社のビジネスの根底にある情熱や物語は何か?それを一つの段落で表現してみる。
- 一貫性監査を行う:自社のウェブサイト、パッケージ、SNSを並べて見てみる。それらはすべて、同じ会社から発信されていると感じられるか?
- 感情的なフックを特定する:顧客に自社ブランドと結びつけてほしい感情は何か?(例:安心、喜び、信頼、興奮)
- 対話を始める:SNSを一つ選び、今週、5人の顧客やフォロワーと対話することを目標にする。売るためではなく、純粋に話すために。