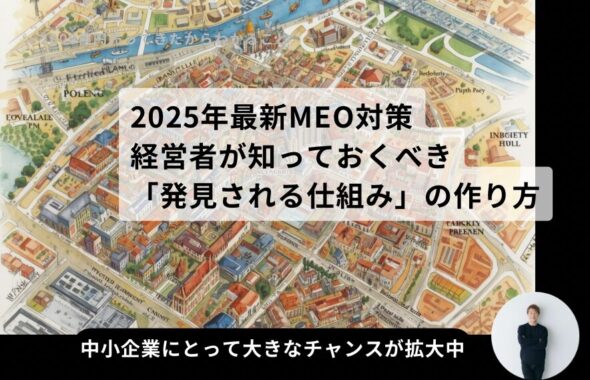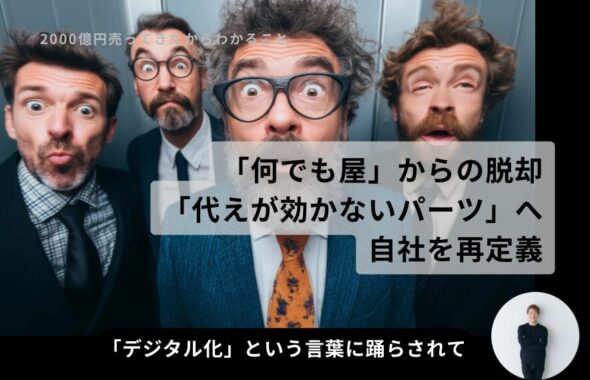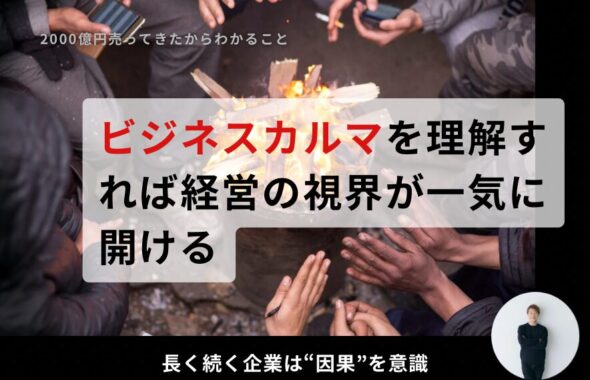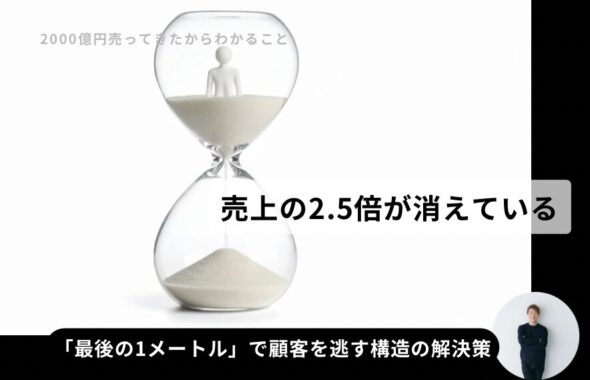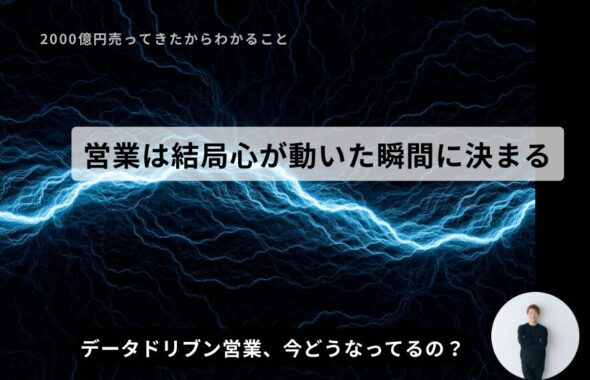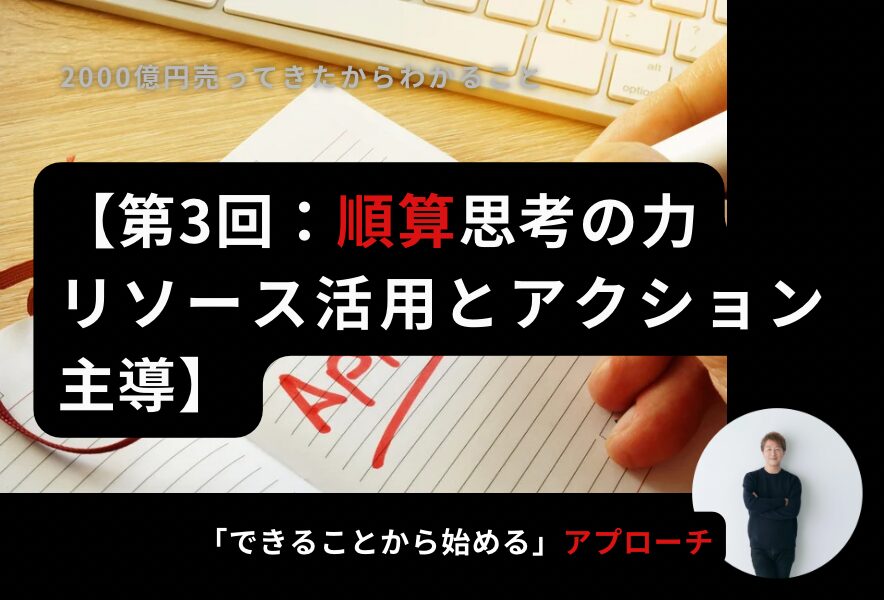
第3回:資源を動かす力|中小企業の成長を生むリソースアクション
以下では、「第3回:順算思考の力―リソース活用とアクション主導」と題し、前回・前々回の内容を受けながら、順算思考(Forecasting/フォアキャスティング)の具体的なメリットや活用法を掘り下げます。
逆算思考(Backcasting/バックキャスティング)との違いを整理しつつ、実務でどのように順算思考を生かすか、事例やポイントを交えて解説しています。
────────────────────────────────
Contents
はじめに
前回(第2回)は、「逆算思考を使いこなす―目標設定と計画の重要性」を中心に、あらかじめ設定したゴールから逆向きに必要ステップを導く手法や、計画立案の注意点・落とし穴などを詳しく見てきました。
一方、現代のビジネス環境では急激な変化や予想外の出来事が多く、いくら綿密な計画を立てても、そのとおりに進めないことがしばしばあります。そこで本稿(第3回)では、逆算思考が苦手とする「不確実性への柔軟な対応」に強みを持つ「順算思考(Forecasting/フォアキャスティング)」を取り上げます。
順算思考は「まず目の前にあるリソースや人脈を活かし、小さく実行しながら学び、次の一手を考える」スタンスが特徴です。これはITスタートアップやイノベーションの現場でよく見られるアジャイル開発にも通じる発想であり、組織が新しいアイデアを素早く試し、成果を得やすくするメリットがあります。
今回は
1) 順算思考の基本概念と利点
2) リソース活用の考え方とネットワーク効果
3) 行動を起点とした学習プロセス
4) 逆算思考との併用による具体的な相乗効果
といったトピックを順に解説します。
────────────────────────────────
1. 順算思考とは?―「できることから始める」アプローチ
1-1. 逆算思考との対比
逆算思考は、「明確な目標(ゴール)を先に定め、その達成に必要な活動を逆向きに落とし込む」方法でした。これに対し、順算思考は「現在持っているリソース・知識・人的ネットワークを活かし、試しながら次へ進む」アプローチです。
たとえば、事業を新しく立ち上げる際、逆算思考なら「3年後にシェア10%を狙うための売上目標」を先に設定して逆向きに必要投資を算出します。
一方、順算思考では「とにかく今ある資金で試作品を作ってみる」「少数のテストユーザーを集めてフィードバックをもらう」といった行動を素早く始め、それによって見えてきた可能性やアイデアを次のステップに活かしていくイメージです。
1-2. 実験と学習のサイクル
順算思考のキーワードは「実験と学習」です。動いてみては結果を評価し、その学びを元に次のアクションを決めるというサイクルを回すことを重視します。
そのため、一度に大きなリソースを投下するのではなく、なるべく小さな単位で市場テストやユーザー調査を進めるケースが多く見られます。
失敗したとしても投じたコストが小さければダメージが少なく、むしろ早期に失敗ポイントを学べるのがメリットと言えるでしょう。
────────────────────────────────
2. リソース活用とネットワーク効果―「今、手元にあるもの」で動く
2-1. リソースを棚卸しする
順算思考を実践する第一歩は、「自分(あるいは組織)が現在持っているリソースは何か」を洗い出すことです。リソースとは、単に資金や設備だけでなく、ヒト(人的ネットワークやスキル)、情報(顧客データ、ノウハウ)、アセット(ブランド、店舗、特許など)を含めた広い概念です。
このリソースを改めて棚卸しすることで、実はすぐに活用できる強みやコネクションが潜んでいることに気づく場合があります。たとえば、過去に取引した小規模顧客と親密な関係があるなら、まずそことの共同開発を試みるなど、小さいながらも具体的なアクションに繋がりやすくなります。
2-2. ネットワーク効果を引き出す
順算思考を多用する企業の中には、「最初の小さな成功」を周囲への実績として示しながら、協力者やパートナーを増やしていくケースがよく見られます。
ここで重要なのがネットワーク効果です。小さな成功事例が一つあるだけで、「この会社は面白い」「一緒に組んだら新しい価値を作れそうだ」と考える外部のステークホルダーが増えていくのです。
逆算思考だと「計画を完遂してから発信する」という発想になりがちですが、順算思考の場合、途中経過や実験結果をオープンに共有することで周囲を巻き込みやすくなります。そこに付随する偶然の出会いや「相手が持つ新たなリソース」が合流することで、当初は想定していなかった展開が生まれる可能性も高まるわけです。
────────────────────────────────
3. アクション主導型の学習プロセス―「やってみてから考える」の効用
3-1. 行動を起点に思考が広がる
一般的に、何かを成し遂げようとするとき、人は先に「考え」→「行動」に移すケースが多いとされます。
しかし、順算思考を実践している企業や個人を見ると、「行動しながら考える」姿勢が際立っています。たとえば試作品を作る前に完璧なプランを練らず、ある程度の段階で「とりあえず作って使ってみよう」と動き出し、実際に触れた反応やデータを元に次の計画を練るのです。
この「行動が先」という順序には、以下のようなメリットがあると考えられます。
• スピード感を維持できる(行動までの時間が短い)
• 実際の手応えや市場のリアルな声を早期に知れる
• 想像や机上の計算では得られない気づきや洞察が生まれる
3-2. 失敗を「小さく」する発想
行動主導にはリスクもつきものです。ただ、大きな投資やプロジェクトを一発勝負で行うのではなく、順算思考では「小さく試す」ことを重んじます。
つまり、成功か失敗かが大きく分かれる前に、小規模のパイロットテストやプロトタイプを通じて検証を行うため、万一失敗しても取り返しがつきやすいというわけです。
たとえば、ある新製品を全国販売する前に、特定の地域や既存顧客だけを対象とした限定テストを実施し、その結果を踏まえて改良を重ねる方法が典型的です。このプロセスを何度か重ねていくうちに、リスクが低減され、成功確率が高まるという流れです。
────────────────────────────────
4. 順算思考が活きるシチュエーション―変化の激しい市場や新規事業など
4-1. VUCA時代と順算思考の親和性
前回(第2回)のラストでも少し触れましたが、現代はVUCA(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)の時代とも言われ、変動性と不確実性が高まっています。このような環境では、事前に立てた綿密な計画(逆算思考)通りにいかないことが多く、むしろ「やってみて微調整しながら進む」順算思考のほうがリスクを最小化しやすい場合があります。
特に、新興企業やスタートアップが試みるようなイノベーション領域では、市場ニーズを完全に予測してから製品開発やサービス提供を行うのは極めて難しいため、順算思考的にユーザー検証を素早く回していくアプローチが定着しやすいのです。
4-2. 新規事業・新規プロジェクトでの導入例
すでに成熟した大企業であっても、新規事業部門やイノベーション担当部署を立ち上げる際には、順算思考に近い手法を採用するケースが増えています。大企業の堅い体質を残したまま壮大な投資計画を打ち出しても、想定外の障害があったときに大きな損失を出すリスクがあるからです。
そこで、小規模のチームを組成し、一定の予算内で試作や実証実験をどんどん繰り返し、その中で芽が出そうなアイデアを少しずつスケールアップしていく――こうした「小回りの利く順算思考型」の動き方が注目されています。
────────────────────────────────
5. 逆算思考との併用による相乗効果
5-1. 小さな成功を積み重ねながら、長期ビジョンに近づく
順算思考と逆算思考は、一見すると正反対の発想ですが、実際には補完関係にあります。特に大きな組織や長期目標がある場合、「3年後のビジョンをしっかり描く(逆算思考)」と同時に、「その途中段階で小規模の実験を繰り返し、結果を都度フィードバックして目標やプロセスを微調整する(順算思考)」の組み合わせが非常に有効です。
たとえば、逆算思考で3年後の売上目標と必要なリソースを割り出したうえで、順算思考による小さなテスト販売を定期的に行い、新商品のラインナップやマーケット開拓を進めるようにすると、長期ビジョンに大きなブレがなく、かつ不確実な要素にも対応しやすくなります。
5-2. リーダーシップと組織文化への影響
順算思考を積極的に取り入れると、組織内に「まずやってみよう」「失敗してもそこから学べばいい」という文化が育ちやすくなります。特に若手社員や中堅社員が主体的に企画を実行し、その結果を共有しながら軌道修正するプロセスが回ると、チーム全体の創造性やモチベーションが高まる傾向があります。
一方、トップや経営陣は、逆算思考で提示した大きな目標や会社のビジョンを定期的にリマインドし、社員が“行き当たりばったり”にならないようにガイドする必要があります。つまり、経営トップが逆算思考で「軸」を示しつつ、ミドルリーダーや現場担当者が順算思考で柔軟に動くという構造が理想的な形の一つと言えるでしょう。
────────────────────────────────
6. 実務における順算思考活用事例
ここでは、特定の企業名を出さずに、これまで私が見聞きした順算思考をうまく活用していた例を、ビジネスの種類ごとにご紹介します。
6-1. ITスタートアップのアジャイル開発
ITスタートアップで、Webサービスやスマホアプリを作る場合には、アジャイル開発が主流となっています。これは短いスプリント(1〜2週間程度)で新機能の試作品を作り、ユーザーの反応を即座にテストして次のスプリントに活かす手法です。
具体的な長期目標(例:3年後に◯百万人のユーザーを獲得する)があっても、一気にすべての機能をリリースするのではなく、小分けにして実装&リリースし、都度顧客のフィードバックを反映させる——まさに順算思考的な進め方です。
6-2. 地域密着型小売店の新商品テスト
ある地方の小売店では、地域密着型の強みを活かし、毎月ごとに「ご当地スイーツ」「地域産のクラフト商品」などの試作を限定販売し、売れ行きや顧客アンケートから得られるデータを蓄積していました。
いきなり大量生産をせず、小ロットでテスト販売することでリスクを低く抑えつつ、当たりそうな商品が見つかったら規模を拡大していく、という流れです。
この「小さく始めて学ぶ」取り組みが評判を呼び、最終的には県外への販路拡大にまで繋がっていきました。これも典型的な順算思考の事例と言えます。
────────────────────────────────
7. 順算思考導入のポイントと注意点
7-1. 「あれもこれも」やりすぎない
順算思考は試行錯誤を奨励する一方で、行動を広げすぎると「どこに集中すべきか」がわからなくなるリスクがあります。組織内で「新規アイデアはすべてやってみよう」となると、リソースが分散し、どれも中途半端に終わる結果になりかねません。
そこで必要なのは、逆算思考で設定した大きなビジョンに照らして「このアイデアはビジョン達成に貢献しそうか?」を判断基準とし、厳選して動く姿勢です。
7-2. スピード重視でも品質を完全に無視しない
「まずは行動」という順算思考は、スピード感が大きな魅力です。ただし品質面を完全に度外視すると、ユーザーの信頼を損なう可能性があるため注意が必要です。
特に外部に公開するテストや試作品では、あまりにもクオリティが低いと誤解や炎上を招くリスクがあります。
アジャイル開発でも「MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)」という考え方が重視されるように、最低限の品質や完成度を持った形で市場テストを行うことが肝心です。
7-3. データ収集と分析の仕組み
順算思考で小さなアクションを積み重ねても、その結果をデータ化・分析しなければ十分な学習が得られません。単なる「なんとなくの印象」に基づいて意思決定を続けると、誤った方向に突き進む可能性が高まります。
よって、テスト結果をきちんと測定し、失敗の原因や成功の要因を可視化するためのデータ収集・分析体制を用意しておくのが理想です。
────────────────────────────────
8. まとめと次回予告―順算思考がもたらす未来
ここまで、順算思考の概念や実践例、導入時の注意点などを解説してきました。主なポイントを振り返ると、次のようにまとめられます。
1. 順算思考は「今あるリソースや人脈からスタートし、小さく行動して学ぶ」発想であり、不確実性の高い環境に強みを持つ。
2. リソース棚卸しやネットワーク効果の活用により、小さな成功を周囲へ伝播させ、さらなる協力者やビジネスチャンスを得やすい。
3. アクション主導型の学習サイクル(行動→評価→学習→改善)が中核となるため、失敗のリスクは「小分け」にしつつ、成功確率を高めるアプローチが可能。
4. ただし「あれもこれも」的に動きすぎると、リソース不足や品質低下を招く恐れがあるため、逆算思考のビジョンをリファレンスに絞り込む姿勢が重要。
5. 順算思考と逆算思考の併用こそが、柔軟性と方向性の両立をもたらし、組織や事業を最終的に大きく成長させる原動力となる。
次回(第4回)は、「統合的運用モデル―両思考法のダブルループ」をテーマに、逆算思考と順算思考をどのように具体的に融合させればいいのかをさらに掘り下げます。
ここまで紹介してきた両思考の特性を組み合わせ、実際のプロジェクトや経営に落とし込むフレームワークや事例、さらにはAIやプロジェクト管理ツールなどを活用したリアルタイム最適化の可能性なども交えながら、「両思考を行ったり来たりする」ダブルループの活用術をお伝えする予定です。
────────────────────────────────
あとがき
第3回では、順算思考(Forecasting/フォアキャスティング)の強みと実践方法を中心に解説しました。逆算思考が「長期ビジョン」によって大きな軸を作るのに対し、順算思考は「行動から学ぶ」姿勢でビジョスをより具体化・現実化していく役割を担います。
実務では、どうしても「目標管理」と「日々の改善活動」が切り離されがちですが、本シリーズで取り上げているように、逆算思考と順算思考を組み合わせた運用こそが、組織の変化対応力と成果創出力を同時に高める要となります。
次回もぜひご覧いただき、両思考を統合して使いこなすプロセスについて理解を深めていただければ幸いです。
────────────────────────────────
以上が「第3回:順算思考の力―リソース活用とアクション主導」の内容です。次回(第4回)は「統合的運用モデル―両思考法のダブルループ」をテーマに、両方の思考を実際のビジネスでどのように同時並行・反復活用するかを探っていきます。引き続きよろしくお願いいたします。