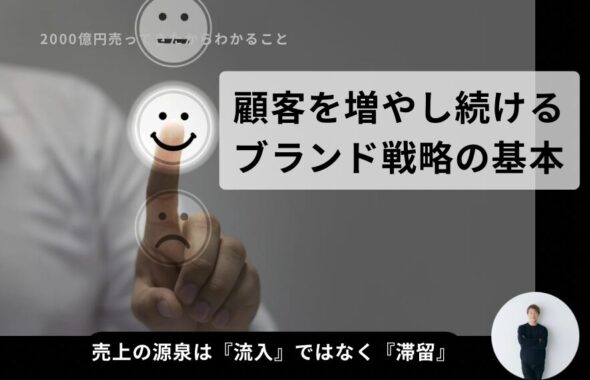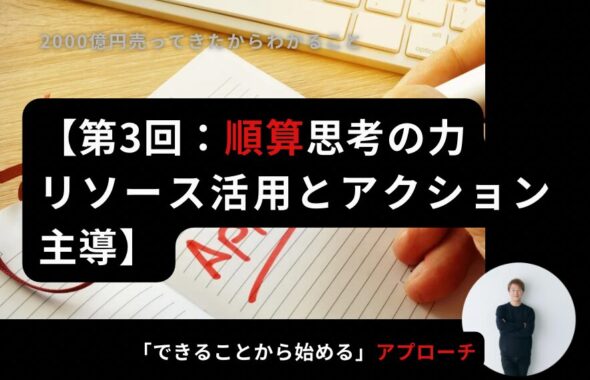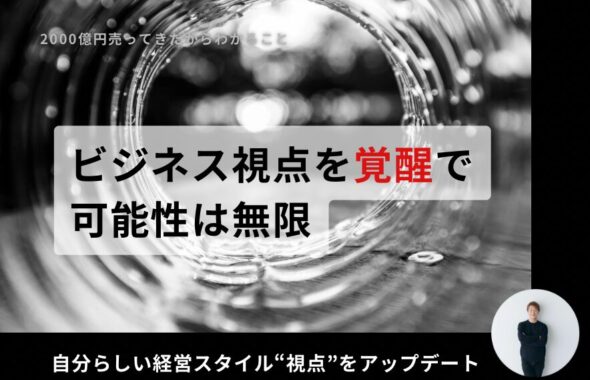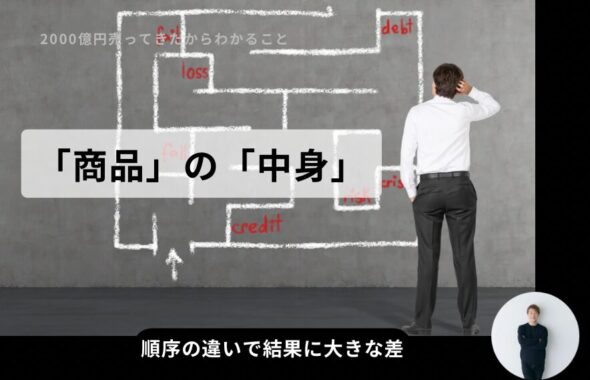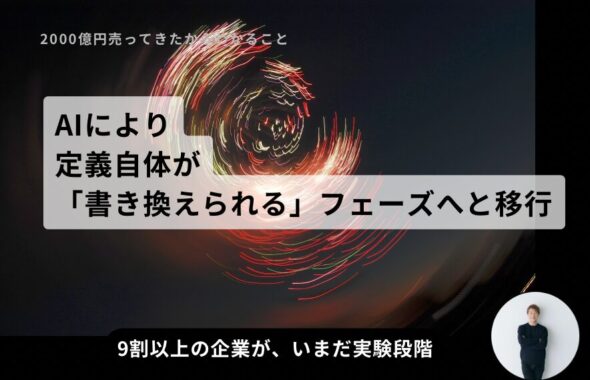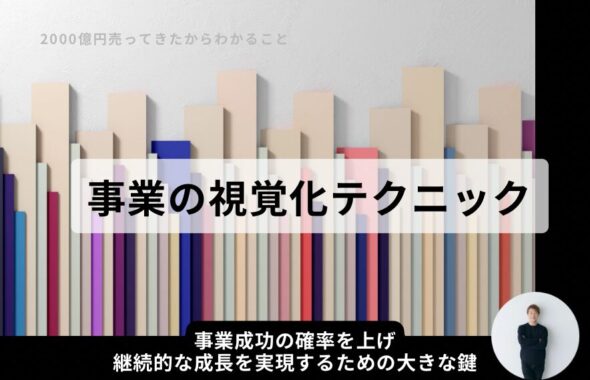【運用診断】御社のTikTokが失敗した「論理的な理由」|センスに頼らず成果を出す再建ロードマップ
Contents
なぜ、あのTikTokは失敗したのか?
売上を左右する“プラットフォーム”と“クリエイティブ”のほんと
「次はTikTokに本格参入すべきか?」「YouTubeの予算をどうするか?」 経営者であれば、こうした「プラットフォーム選定」の議論に多くの時間を割かれていることでしょう。
しかし、もしその議論の前提が、根本的に間違っているとしたらどうでしょうか。
「売れる・売れないの差は、使うプラットフォーム(配信場所やチャネル)ではなく、そこで使うクリエイティブ(広告や投稿の『内容』)の差である」
これは、多くのマーケティング現場、そして経営層が見落としている、最も重要な事実かもしれません。
もちろん、ご指摘の通り、プラットフォームには商品との「相性」があり、売上までの「スピード」も異なります。しかし、それらは“売上の本質”ではありません。
本日は、データに基づき、経営者が本当に注力すべきアジェンダについてお話しします。
経営会議の「9%」にリソースを割いていませんか?
マーケティングの成果を分析する上で、非常に有名な調査があります。
世界的な調査会社であるNielsen(ニールセン)が500の広告キャンペーンを分析したところ、売上への貢献度のうち、実に47%が「クリエイティブ」によって占められていました。 一方で、経営陣がしばしば固執する「ターゲティング」(どのプラットフォームで、誰に当てるか)の売上貢献度は、わずか9%だったのです。
他の調査でも、Kantar(カンター)は49%、Google(グーグル)は70%の売上貢献がクリエイティブによるものだと言及しています。
私たちは、売上の9%しか説明できない要因に、議論とリソースの大半を割いてしまっている可能性があります。
「プラットフォームのせい」にする組織が陥る罠
このデータには、さらに重要な続きがあります。Nielsen(ニールセン)は、クリエイティブを「強いクリエイティブ」と「弱いクリエイティブ」に分けて分析しました。
その結果、「強いクリエイティブ」は、デジタル広告において成功要因の最大89%を占める、文字通り圧倒的なドライバーとなりました。逆に「弱いクリエイティブ」の場合、売上リフト(向上)は弱く、その(わずかな)成功は「メディア要因」(プラットフォームやターゲティング)に依存する結果となったのです。
これは、経営者に重大な問いを突きつけます。
もし、あなたの会社が「TikTokで試したが、うまくいかなかった」「あのチャネルはダメだ」とプラットフォームのせいにしているとしたら、それは、自社のクリエイティブが「弱い」ことを暗に証明している可能性があるのです。
弱いクリエイティブしか生み出せない組織では、メディア(プラットフォーム)の最適化(売上の9%の要因)しか、改善のレバーが残されていないのです。
なぜ経営者は「プラットフォームの罠」に陥るのか
では、なぜ多くの優れた経営者でさえ、この「プラットフォームの罠」に陥ってしまうのでしょうか。
1. 「インフラ戦略」と「チャネル戦術」の混同
経営者が「プラットフォーム」と言う時、それはしばしばAmazonや楽天、あるいは自社EC(電子商取引サイト)のような「事業基盤(インフラ)」を指しています。顧客データを蓄積し、囲い込むという「インフラ戦略」は、経営上、極めて重要です。
しかし、マーケティング現場が言う「プラットフォーム」とは、TikTokやFacebookのような「広告配信チャネル(戦術)」です。
「インフラ戦略」の重要性を、そのまま「チャネル戦術」に当てはめてしまい、「TikTokを使えば勝てる」と誤解してしまうことが、判断の歪みを生みます。
2. 現場の「CPA高騰」への恐れ
経営者からの「CPA(Cost Per Acquisition、顧客獲得単価)を維持しつつ、売上を伸ばせ」というプレッシャーは、現場の視野を狭めます。
現場はCPA高騰のリスクが低い「顕在層(けんざいそう、すでに買う気のある層)向け施策」—すなわち、Google検索広告やリターゲティング(一度サイトを訪れた人に広告を出す手法)といった、「すでに買う気のある人」を刈り取る手法—に偏重します。
この領域では、クリエイティブが弱くても「買う気のある人」がクリックするため、あたかも「Googleというプラットフォームが売上を作った」かのように見えます。
しかし、これは成長(スケール)ではなく「刈り取り」です。すぐに限界が来ます。この小さな成功体験が、「プラットフォームこそが重要」という経営者の信念を強化してしまうのです。
プラットフォームの「正しい」使い方:『相性』と『スピード』
では、プラットフォーム選定は無意味なのでしょうか? 決してそうではありません。
ご指摘の通り、プラットフォームごとの「相性」と「スピード」を理解することは、クリエイティブを活かすための「前提条件」です。
重要なのは、プラットフォームを「売上を生む魔法の箱」ではなく、「クリエイティブを届ける文脈(コンテクスト)」として捉え直すことです。
1. 「スピード」の正体 = ファネルの深さ
「売上までのスピード」の違いとは、顧客の購買プロセス(「ファネル」と呼ばれます)の「どの段階」の顧客に触れるかの違いです。
- スピードが速い(例:Google検索): 「行動(購入)」に近い顕在層にアプローチします。市場(顧客数)は小さいですが、すぐに売上になります。
- スピードが遅い(例:TikTok): 「認知・興味」の「潜在層(せんざいそう、まだ製品を知らない層)」にアプローチします。市場は大きいですが、売上(行動)まで時間がかかります。
経営者は、自社が今、スピード(刈り取り)を求めているのか、スケール(開拓)を求めているのかによって、プラットフォームの役割を定義する必要があります。
2. 「相性」の正体 = ビジネスモデルと“文法”
「相性」は、ビジネスモデルと、プラットフォーム固有の「文法(ユーザーが期待する暗黙のルール)」によって決まります。
- BtoC(企業から消費者へ)のファッション分野: Z世代の6割以上がSNSで商品を「認知」し、比較・検討を行います。プラットフォームは「発見の場」です。
- BtoB(企業間取引)のSaaS(サービスとしてのソフトウェア): 検討期間が長く、関与する人数も多いのが特徴です。プラットフォームの役割は、リード(見込み客)を獲得し、「教育(ナーチャリング)」することにあります。
- 地域密着型ビジネス(医療、飲食): デジタル(リスティング広告や地域ポータルサイト)とアナログ(交通広告など)を組み合わせ、「商圏内の信頼」を勝ち取るクリエイティブが求められます。
そして最も重要な「相性」がプラットフォームの「文法」です。
例えば、Facebook広告で成果が出た「作り込まれた高品質な動画」を、そのままTikTokに転用しても、それは「文法」違反であり、ユーザーから即座にスキップされるでしょう。TikTokには、ユーザー投稿(UGC、User Generated Content)に馴染む「広告らしくない」クリエイティブという「文法」があるからです。
プラットフォーム選定とは、「場所選び」ではなく、「そこで話すべき『言語』の選択」に他なりません。
経営者が今、下すべき「唯一の」決断
売上の47%以上を占める「クリエイティブ」を、これ以上「センス」や「アート」といった主観的な領域に放置してはなりません。
経営者が今、下すべき決断は、「どのプラットフォームに乗るか」ではなく、「自社の『クリエイティブ』の質を定義し、それを客観的に測定し、改善し続けるインフラと組織に、今すぐ投資する」ことです。
そのために、経営者は3つの問いを立ててください。
- 【評価】クリエイティブを「客観的」に測定しているか? 「効果を測定する方法を一切持っていない」マーケターは33%もいるという調査結果があります。これでは議論になりません。今は、AIを活用した「アテンション技術」(注意・関心)など、クリエイティブのどの要素が視聴者の注意を引きつけたかを可視化するソリューションも登場しています。クリエイティブを「サイエンス(客観)」の領域で管理するツールやBI(ビジネスインテリジェンス、データを分析・可視化するツール)への投資を承認してください。
- 【予算】『チャネル別』ではなく『目的別』になっているか? 「リスティング広告予算」「SNS広告予算」といった「チャネル別」の予算組みは、プラットフォーム偏重の元凶です。「新規顧客獲得(潜在層)予算」「既存顧客刈り取り(顕在層)予算」といった「目的別」の予算組みに変革してください。そして、成果の出ていない施策の予算を、勇気を持って新規施策(潜在層向けクリエイティブ開発)に投下してください。その際、媒体の機械学習(広告プラットフォームのAIによる自動最適化)が最適化されるまでには時間と予算が必要だと理解し、短期的な結果で判断しないことが重要です。
- 【組織】『機能別(サイロ)』ではなく『アジャイル』になっているか? 「SEOチーム」「広告運用チーム」「SNSチーム」といった「機能別」組織は、部門間の連携を阻害し、部門が縦割りになる「サイロ化」を招きます。企業の規模にもよりますが、クリエイティブの仮説検証を高速で回せる「アジャイル型組織」(迅速に仮説検証を回す組織)や、製品ごとに最適な戦略を一気通貫で実行する「プロダクト別組織」(製品・サービス別の組織)への見直しを検討してください。
結論
プラットフォームのトレンドを追いかけることは、他社と同じ土俵で、他社と同じルールで戦うことです。Amazon、Google、TikTokのルールは、明日にも変わるかもしれません。
経営者が真にコントロールできるのは、メディア(プラットフォーム)ではなく、自社の「クリエイティブ(=顧客への提供価値の表現)」だけです。
「なぜ、あのTikTokは失敗したのか?」——その答えは、TikTokにあるのではありません。
「なぜ、我々のクリエイティブは、顧客の心を動かせなかったのか?」
この問いこそが、持続的な成長を実現する唯一の鍵となります。